
働きながら学ぶ人を紹介する「先輩インタビュー」今回は東京大学大学院学際情報学府で学ばれた宇田川敦史さんです。
デジタルメディアのサービス開発に携わりながら、ユーザーファーストを追求し切れぬ矛盾を抱える日々。解決法を模索し続けるうちに、1つの会社やサービスの問題ではなくそれが社会の問題なのではという新たな課題に出会います。ポストペットを観察するがごとく人々のデジタルメディアコミュニケーションを俯瞰し分析する宇田川さんの視点はとても温かくそしてユニーク。アカデミックの領域から、社会に何を投げかけて下さるのでしょうか。
京都大学総合人間学部を卒業後、日本IBMにてWebアプリケーションの設計・開発に携わる。その後楽天にてデジタル・マーケティング、UXデザインに従事しながら、2016年より東京大学大学院学際情報学府に入学。研究者への転身をめざして博士課程に進学し、2022年より武蔵大学社会学部メディア社会学科准教授に着任。著書に『ソーシャルメディア・スタディーズ』(2021年、北樹出版、分担執筆)。
卒業・修了した大学・大学院:東京大学大学院学際情報学府
修士入学年月(年齢):2016年4月(38歳)
修士修了年月(年齢):2018年3月(40歳)
博士入学年月(年齢):2018年4月(40歳) 在学中
●ポストペットにハマる人間の観察にハマる
————まずは学部時代のことをお伺いしたいです。
京都大学総合人間学部という、できて5年目ぐらいの学部に居ました。当時「学際」と呼ばれる文系と理系が一緒になった学部はまだ珍しく、ここはその「はしり」という感じでした。学部の中に社会心理学とコンピュータサイエンスが一緒に入っているようなコンセプトの場所で、私はその中でも「グループダイナミクス」という領域に携わっていました。
所属していた研究室では、いかに地域コミュニティを活性化させるか、そこでのアクションリサーチはどのようにあるべきか、といった実践的な研究をする中で、コミュニケーションやコミュニティをいかに構築していくか、といったことに関わっていました。当時はそれまでの実験心理学に批判的な「社会構築主義」や「社会構成主義」などが出始めたころで、私の指導教員の先生も、フィールドワーク重視の心理学をやっていました。
ところが私自身は「地域コミュニティ」よりは、当時流行りだしたインターネットに興味がありました。インターネットがどういうコミュニティを作っていくのかを研究してみたいと指導教員に相談してみたら、とりあえずやってみたら?という感じで(笑)
当時「ポストペット」というSONYのメールソフトがあったんです。殺風景なWindowsマシンの中で、コミュニケーションをある種擬人化するようなツールとしてインターネットにでてきたわけです。
メタバースもセカンドライフもなければ、アバターもない時代です。むしろこういうのがインターネットらしさだ!と感じて、それを研究していました。
ポストペットをめぐるネット上の書き込みはとても興味深く、「ペットがかわいい」「ペットにお手紙をもらった」などとにかくハマっている人々がいる。そういうゲームの中でメールをやりとりするゲーム、つまりゲーミフィケーションなんですけど、それにはまっていく人たちがどういうふうにはまっていくのかみたいなことをネット上のケーススタディとして分析する、みたいなことをやってました。
————面白いですねぇ。宇田川さんもそれが好きだったんですか。
一緒にやってましたが、どちらかというと、ポストペットにハマっている人たちを見るのが面白くて興味を持ち「なぜこんなにハマっていくのだろう」と調べたくなったという感じです。
デジタルメディア上でのコミュニケーションがどのように構築されるのかというところには、ずっと関心があるんだと思います。
当時京都大学に大澤真幸先生という社会学者がいて、理論的な社会学をみっちり勉強できたんですね。社会学理論とインターネット現象みたいなものを結びつけるといったことを卒論で取り組んでいました。
「社会学理論とインターネットコミュニティ」が自分の関心のコアにあったって感じですかね。
————それって20年ぐらい前ですよね。もうその当時からそういうことを考えていた人がいたんですね。......すごいなあ。
我々の世代がそういうことに敏感な世代だったのもあると思います。
よく「デジタルネイティブ」と言いますが、よく言われるのはスマホが物心ついたときからある世代のことですよね。我々の場合は、小学校に入ったときにファミコンが出てきて、その後パソコンをみんなが使うようになり、大学でインターネットデビューして携帯もそのころ入ってくる。そういうものが入ってきたのをリアルタイムに経験している世代です。だからこそ関心が強い人が多いのかもしれないです。
————IBMに入社されたのは、そういった学部での関心を活かしたいという思いがあったんですか。
当時インターネットは、まだアマチュアのものでした。アマチュアで一番先頭を走るのって大学生ですよね。企業もあまり使っていない当時は、大学生がインターネットを最も知っているような時代でした。すると大学生がアルバイトでHTMLを使ってホームページを作るんですね。当時はCGIといって、掲示板みたいなものを自分でプログラムを書いて動かしていました。
私がIBMに行こうと思った一番の理由は、バイト先でたまたま別のシステム開発をする現場に立ち会うことがあり、SEの人たちが話をしているのを見る機会に恵まれたことです。「この仕事面白そうだな」と思いました。こういうSEの現場にもインターネットが入ってくるだろうと思い、就職しました。
————ここで開発に興味を持たれたわけですね。ご自身でひたすら書くというよりは、プロジェクトマネジメントやITコンサルといった工程に関わっていらっしゃったのでしょうか?
そうですね。当時SI(システム・インテグレーション)の会社は、自分たちでプログラムを書くというよりは、受注したプロジェクトをマネジメントするのが基本的な仕事だったんですね。IBMに入ってSEといえば基本的にプロジェクトマネジメントをするという感じでした。システムのプロジェクトの進捗管理をしたり、「要件定義」という、画面の設計をするときのお客さんのニーズをヒアリングしたりといった上流の工程に関わっていました。
————楽天への転職のきっかけは何だったのでしょうか?

IBMにいたころから、BtoCのサービスをやりたいと思っていましたが、なかなかチャンスがなく、BtoBの仕事がほとんどでした。要件定義して作るものは自分が使うシステムではなく会社の人が使うシステム。そこに何となく限界を感じ、どこかで自分自身や、友達に使ってもらえるようなものを作りたいという思いがありました。これ、ものづくりあるあるだと思いますけど(笑)。それならば事業会社へ行った方がいいと考えて、ネットの事業会社をいくつか転職先として探して、楽天に採用してもらえました。
●問題は会社ではなく社会にあるのではという問い
————進学へのきっかけは、転職先の楽天で生まれたのでしょうか?
楽天では「データサイエンス」という言葉がないころからデータサイエンスっぽいことをしていました。データベースに基づき、ユーザーの反応によってアクションを作っていくというやり方です。
一番わかりやすい例はメルマガです。楽天はメルマガがとにかく多くて有名で、しかも解除しにくくてすごく不評(笑)。自分でも嫌だなと思っていましたが、嫌だなと思っているのになぜやるのかを突き詰めていくと、結局儲かるからやっているんですよね。
デジタルマーケティングの観点でいうと、送るコストがかからず、反応率が1%でもあるならば、100万人より1000万人に送った方がいいという話なんです。何回も送った方が反応してくれる数も上がる。従って基本的には送った方が儲かる。感情的な部分には様々あるかもしれないが、結果的に買ってくれてるということはユーザーが満足してるのだろう、というけっこう乱暴なロジックが2010年ぐらいのネット企業では割と真面目にまかり通っていました。
私は「自分は本当は欲しくないものを、提供しなければならないこの矛盾は何なんだろう」というモヤモヤがすごく大きくて、それはどこかで解決したいと思っていたんです。
社内では、自分の仕事をマーケティングからUXデザインの方にシフトしていき、ユーザーの利益や満足とは何かをある程度追求できる立場に動いていってはいました。しかし、最終的にコンバージョンレートや売り上げが大事ということは、根本的には変わらない。それはつまり、そもそもこのサービスや会社の問題ではなく、そういう社会の問題ではないのかと考えたのです。
————そもそもメディアのあり方から問い直さないと、一社が頑張っても駄目だと。そこにお子さんの「小1の壁」が重なって進学されたということですね。
5〜6年いると大体会社のこともわかってきて、それなりのマネジメントを経験し、自分の裁量である程度できるようになってくる。その次のステップとして、管理職や経営陣の世界になっていくことを考えると、この矛盾を抱えたまま人の上に立つ経営サイドに行くのは、自分のキャリアとしては納得感がないと思ったんです。売上利益のことを最優先に考えなければいけない立場に立たされる。現場は矛盾をわかりつつやってる。自分だったらそこで頑張れないだろうなと思ったんですよね。
それならば自分はスペシャリスト方面に行くか、もしくはもう別の道を考えるかっていうことも考えていて、だったら今の仕事をやめて、家事・育児をしながら勉強するか、という感じでした。
————今のお話、全経営者の方々に聞いていただきたいです!
(笑)でもそれはね、みんなすごい矛盾を抱えながらどこかで割り切らねばと思っていると思いますよ。
でも自分はそっちじゃない。それならば社会人出身の研究者がいいのではないかと思ったんです。最初から研究者になるつもりで、学び直して会社に戻ってくるという意識はあまりなかったように思います。結局自分の抱えている問題は、雇用関係の中で会社にいる限りは解決しないだろうと思いました。戻るにしても外から戻ってこないと駄目だろうと。
研究者としてある程度拠点があり、自分の裁量でコミュニティが作れたら、企業に対して新しい考え方を表明していく方がやりやすいのではないかと思ったんです。
————考えても踏み出せる人ってなかなかいないと思うのですが、そこはもう「いけるな」っていう感覚があったんですか。
いえ、ずっと迷っていました。ですが当時「リーディング大学院」という、基準を満たすと博士まで5年一貫でお金がもらえる制度があったんです。その制度に乗ると、月20万ぐらいもらいながら博士までいけることを知り、これなら行けるのではと思ったんですね。結果的にはその制度を使いませんでしたが、踏ん切りをつけられたのはそういうものがあったからですね。
大学院に合格したあと「大学院に行きます。平日の昼間だから会社を辞めます」と伝えたんです。すると「本気でやるなら仕事をうまく時間調整して、大学と両立できるように考えるよ」と上司が提案してくれたんです。リーディング大学院を検討していましたが、それでお金もらえるならばと、正社員から契約社員に契約を変更しました。パートタイムという形で週に3日程度で、M2のときは毎日午前中だけ出勤するという贅沢な勤務形態にしてもらって、午後は修論を書き、夕方からは家事育児、という恵まれた環境でした。結局、今の大学に就職するまでずっとパートタイムで残ってたんですよ。
●学術研究に対する姿勢を問われる入試
————受験準備についてお伺いします。学部時代にお世話になった先生に相談をして、学環の先生を紹介してもらった、とのことでしたよね。
これ結構大事なことだと思うのですが、すごい思い込みがあったんですよね。
大学院というのは指導教員にまずコンタクトを取らなくてはいけないので、何とかつてをたどってたどり着かなければと思ってたんですが、今思うとそういうことは大事じゃなかったんです。少なくとも東大の学際情報学府の場合は、コネを使ってご挨拶ということは誰も重視していなかった。
紹介してもらって連絡したけど「個別の対応はしないから説明会に来てね」って返事がきたんですよね。それはある意味フラットだったということでもあります。
後でわかったことですが、そこはフェアであることを大事にしているということでした。事前に話を聞きに来たかどうかと全く関係なく、入試のときのパフォーマンスで見ると。それは先生によっても違うと思いますけどね。
————違うんですね。それってどうやって外側から判断するんですかね。

大学院によって入試のやり方がだいぶ違うと思います。
学際情報学府の場合は、研究計画がかなりのウェイトを占めていて、研究計画の提出に加えてそのプレゼンがあるんです。専任の教員が5人ぐらいいて、その前でプレゼンするんですよね。目の前に第一人者が5人いるわけですよ。質問攻めにされるので、そこでかなり判断されているのだと思います。
それだけの人を揃えて2~30分かけて審査すれば、もう分かるだろうな、という感じです。単純な学力を見ているわけじゃないんですよね。姿勢を見られていると感じました。学術研究に対するスタンスや、その人が2年間ちゃんと継続的に研究できるかというある種の謙虚さを含めた探究心みたいなことも必要だし、学びたい姿勢の方向性がずれてないかっていうことを見てるんだろうなと思います。
よく研究と勉強は違うみたいな話が出てくるんですが、勉強だけしたい人だと、大学院としては行き詰まるみたいなところがあって、研究をやり遂げられる人かっていうことを、そのやりとりで判断してるんだろうなっていう感じはしますね。
————そこは勘違いしている人が多いですよね。教えてもらえると思って入ってきちゃう人とか。
知識を教えてもらう場所ではないですからね。知識を生産するための技法を一緒になって考える場だから、そこをちゃんと理解できるかどうか、入試の段階で全部理解できなくてもそこにちゃんとスイッチがあるかどうかってことだとは思うんですよ。
だから「受験準備としてこういう勉強をしました」みたいなことだけではないからなかなか難しいですよね。
————実際に大学院で学ばれて、研究されたということで、その内容自体も、ご自身の問題意識の解消には繋がってるなという実感はありましたか?
みなさんそうだと思いますが、大学院に入る前に思ってた問題意識なんて、かなり薄っぺらい(笑)。修士は、そこを2年かけて何が問題だったのか考えるみたいな期間です。そういう意味では、最初に抱いた問題意識が解決されたかといえば、そうではなく、本質的には違う問題に取り組まなくてはならなかったことがわかるようになった。ということかなと思います。
リサーチクエスチョンは、元々考えてるような漠然としたものではなく、かなり絞り込まないとどうにもならなくて、それは入って初めてわかることです。その結果として絞り込んだ対象が「検索エンジンランキング」だったのですが、自分の元々の原体験を素材にしながら、それを学術的な問題意識と接続できるような何かをみつけていくっていうのが実態かなと思います。
————漠然としたものから、ランキングというものに絞っていった。検索エンジンについて透明化というふうに書かれてましたよね。ランキングの透明化を読んで、確かに意識せずに検索してるなあと思いました。
そうなんですよね。
最終的にはもともと持っていた問いとつながるのですが、結局人はなぜネットでお金を使うのかというところや、クリックしたりするのか、ということが必ずしも理性的・合理的な判断の結果として起こるわけではなく、あまり考えずに行動した結果が蓄積される。実はそれはメルマガも一緒で、結局クリックされてるんだから、クリックされるものを送ればいいという話になっているんです。
それは企業が悪意を持ってるということではなく、その社会のシステムの中で、ユーザーになる人たちも、あまり意識せずいろんな行動していることの蓄積なのだろう、という側面がある。それを「検索エンジン」というものにフォーカスすると、クリックすることに対する意識のなさが浮き彫りになってくる。それはそれでそういうふうに繋がったんだなっていうふうに思いますね。
————ちなみに今ご研究されているのは、どういった内容になるんですか。

Googleを研究対象としているのですが、SEOの歴史ですね。
GAFAなどのプラットフォームって悪者にされがちですよね。彼らがすごく支配的な立場を持っていて、すごく独占的だから、彼らが都合がいいように情報を操作してる印象が社会全体で広がっている。それは半面正しくて、半面間違ってることをちゃんと認識する必要がある。
メルマガを大量に発行している主が悪、という単純な理解ではなく、受け手の人たちもそれに合わせて行動してるから結果的にそうなってるというダイナミズムを理解していく必要があるんだっていうことですね。
Googleの場合はどうなのか。SEOでオウンドメディアとかやると必ず出てくる問題で、かつては嘘を書いてもコピペを作っても順位は上がったし、あるいはリンクをお金で買ってくるとか、そういった問題が山積していました。2000年代の初期、昔はそういうSEOが「いいSEO」で、SEOはそうやって順位を上げれば良いと実際みなさん言っていたんですね。
そういうことが積み重なり、Googleのアルゴリズムとしてどうしていきたいと考えるかという話が出てきて、だんだんそういうブラックハットみたいなものを止めてちゃんと品質を考えたものにして行こうという動きが出てきた。そうすると、急にGoogleが言っているガイドラインとかスタンダードが「実はユーザーのこと考えてるんですよ」と言ってくるから、「みんな、それに従おう!」とトーンがどんどん変わって行ったのです。それがいいか悪いかは別として。
Googleという巨人が一方的に命じて今のWebの生態系ができているわけではなく、そこでWebを作ってる人たちが一緒になって、問題を起こしたり使ったりしながら、結果的に出来上がったのが、現在の「Google様よろしくね」という状態だというわけです。
みんなが協力しあっていろいろぶつかり合った結果、最終的にはみんながここに協力をして出来上がってきた体系っていうのがある一方で、それに対してGAFAが支配的で悪者だっていう批判がでてきたりもする。そういうものを可視化できると面白いなと思ったんです。
————確かにすごく簡単に解釈するとメルマガと似てるんですね。みんなが開封するからそれが送られているわけであって、ということに似ている。
フェイクニュースとかデマとか炎上とかいう問題と一緒で、あれはクリックされる・人気が出るっていうことが可視化されてしまうので、結局広がらなくてもいいのに広がってしまう。1人1人が「これは正しいのかな」と考えられたら止められるんだけど、面白いからとクリックして、正しいかどうかは知りません、という人たちが多すぎると止められなくなってくるのであって、それをTwitterだけが悪いっていうのはちょっと違うだろうと。
————いやぁ面白いですね。社会構成主義とかともつながるのかなと思いました。
そうですね。まさしく社会構成主義とか社会構築主義の話で枠組みは考えていますね。
●研究者を目指す人に伝えたいこと
————非常勤講師は自分で積極的に探して、そっちの道に行かれたんですか。
こういう情報が流れてないので、ちゃんと言った方がいいと思うんですけど、やっぱり研究者として就職しようと思ったら、東大のような研究大学が強いです。これは制度や教育の内容も当然ですが、研究コミュニティとの距離が重要で、博士を育成して最終的にどこかの研究職に就職させることに関しては、国立の研究大学の方がある程度整っている。整っているというよりは先生も含めたコミュニティの力がある。これは、良くも悪くもそうですね。
ただ自分の場合は指導教員の先生のネットワークから非常勤講師の口を紹介してもらうことができたんですね。もちろん論文や学会発表などの実績を積んだ上でですが、博士を目指していることを周囲に知ってもらっていると、指導教員を含めた研究コミュニティから声がかかるようになる。周囲の博士学生は何人かいましたが、誰かの紹介で非常勤が回ってくる。普通に一人で探すとそこはすごくハードルが高いところなので。それはある意味既得権益かもなとは思いますが難しいところですね。
最初からそういったことを目指すのであれば、ある程度人脈を作る必要があるというのは意識した方がいいのかなってのは今になってわかることですね。
大学院の規模の大きいところだと、OB・OGがいて、かなりの確率で大学の教員になってるんですよ。そうすると、同窓生同士で研究会みたいなものがあることもあるので、そういうところに行って、いろいろ教えてもらったりできる。自分の場合は、サバティカル(研究のための休暇)の時に非常勤やってくれない?と声をかけていただいたこともあります。サバティカル中の代打っていうのはピンポイントなので紹介で決まる場合も多いです。
————サバティカルが狙えるといいですね。「既得権益」と言いつつもその優秀な人が集まってるから、「いい」既得権益だからいいよね、と思います。
客観的な評価は難しいですけどね。少なくとも研究職にネットワークがある大学院とか研究室、というのは重要だなと思います。来たからには博士に育てよう!みたいなそういうモードを持ってる研究室を最初から目指すのであれば狙った方がいいですね。
そういう意味でも国立が強いと思います。
それからもう一つ、これは大きかったなということがあって。
指導教員の先生が学会の理事をやったんですよ。そのとき事務局の仕事をしたんです。そうするとその学会というか、その領域の第一人者の人たちが集まる理事会でみんなと顔を合わせるんですよね。
私は議事録を取ったりコーディネートをしたりするのですが、それでも顔を覚えてもらえる。学者のコミュニティは狭いので、顔が知られてるって重要なんですよね。
————学会のコミュニティで気になったのですが、アカデミックと実践の距離が近くなることを嫌う方って多いんでしょうか?実践からアカデミックに流れてくるとか、社会人がたくさん流れ込んでくることを皆さん嫌がるものでしょうか?

それは領域によると思います。私の場合はメディア関係なので、そもそも社会人出身者が多くいるところで、あと学際情報学府も割とそういうところなので、そういうディスアドバンテージはないかな。むしろアドバンテージが大きいですね。
実務経験とセットでアカデミックスキルを博士レベルまで持ってる人が少ないので、そこはむしろアドバンテージがあるかなと思います。領域によるとは思いますが。
あとね、これはあるあるですが、社会人経験をしているからと「偉そうにしてる人」はうまくいかないかも(笑)。これはホントにあるある。
研究者としては未熟者なので「一緒の土俵で学ばせてください」という意識がちゃんとあれば、そんなに失敗することはない。「自分はこんな有名企業でこんなすごい業績があったんだ」みたいな話は全然関係なくて、「いやぁ、今論文書いてるけどここの解釈が難しいんだよね」みたいな話をちゃんとできる人じゃないとダメだと思いますよ。


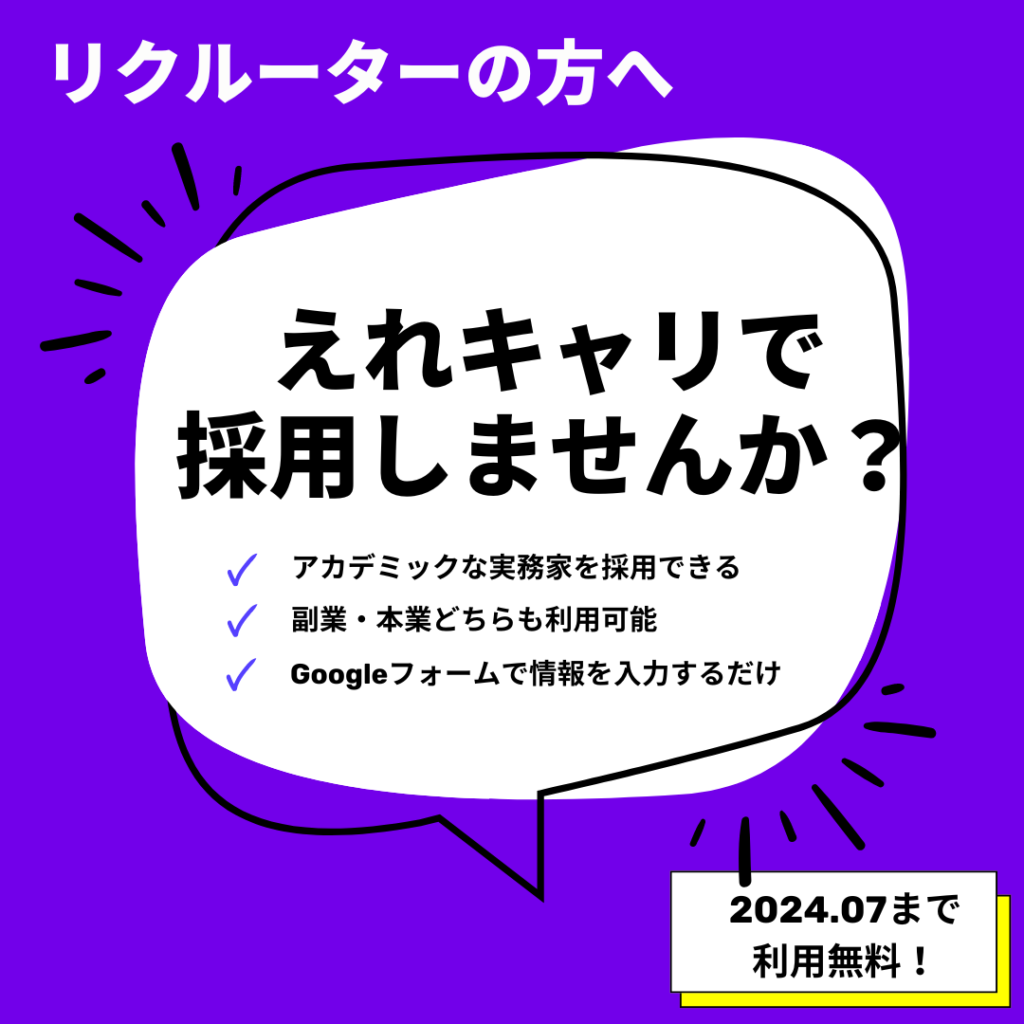

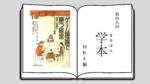
![[体験談] 働きながら大学院で学ぶ大人達のインタビューまとめ2022年11月](https://ele-careers.com/wp-content/uploads/2022/12/13ec775fe2846fb385353200790cbd9e-150x84.png)
