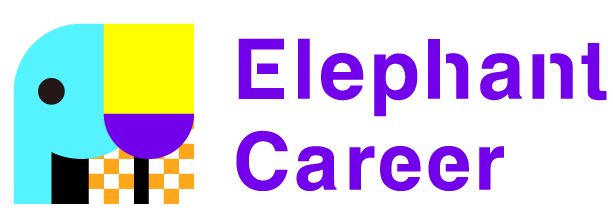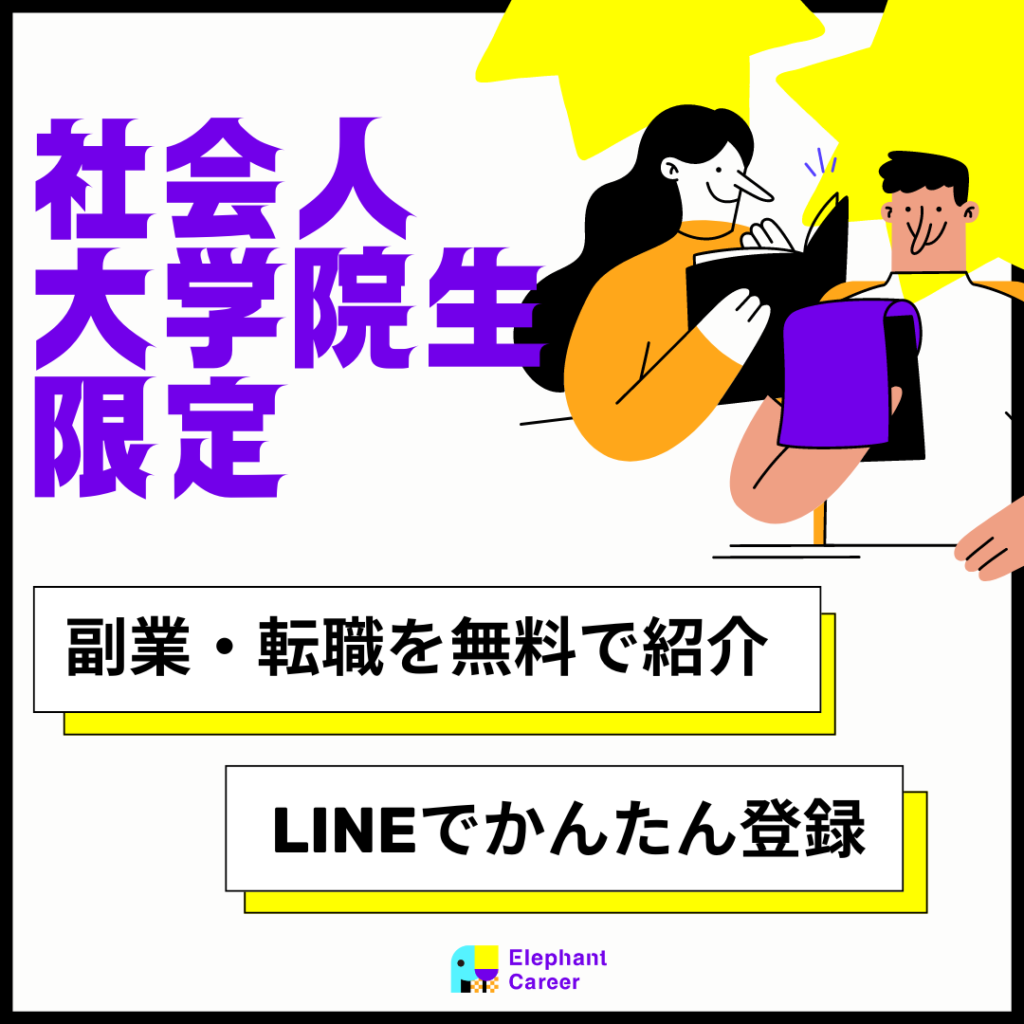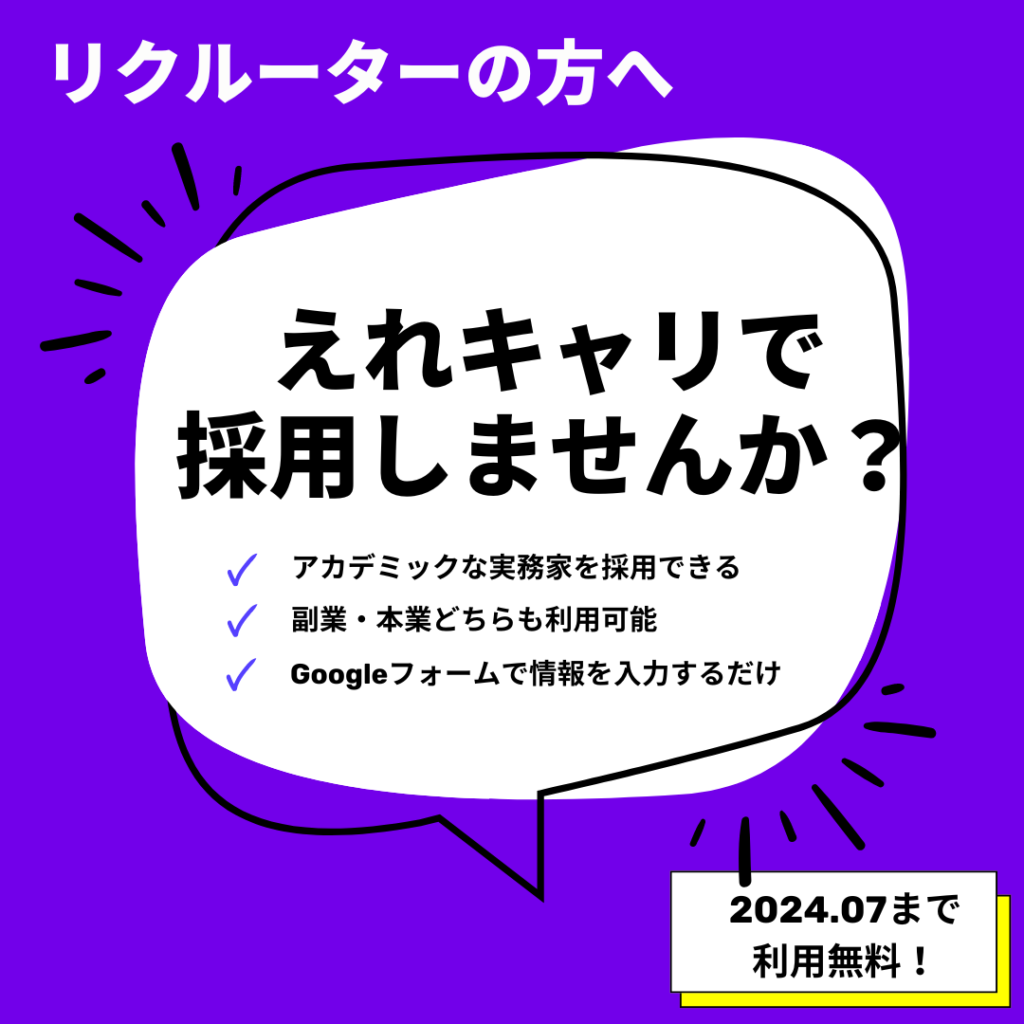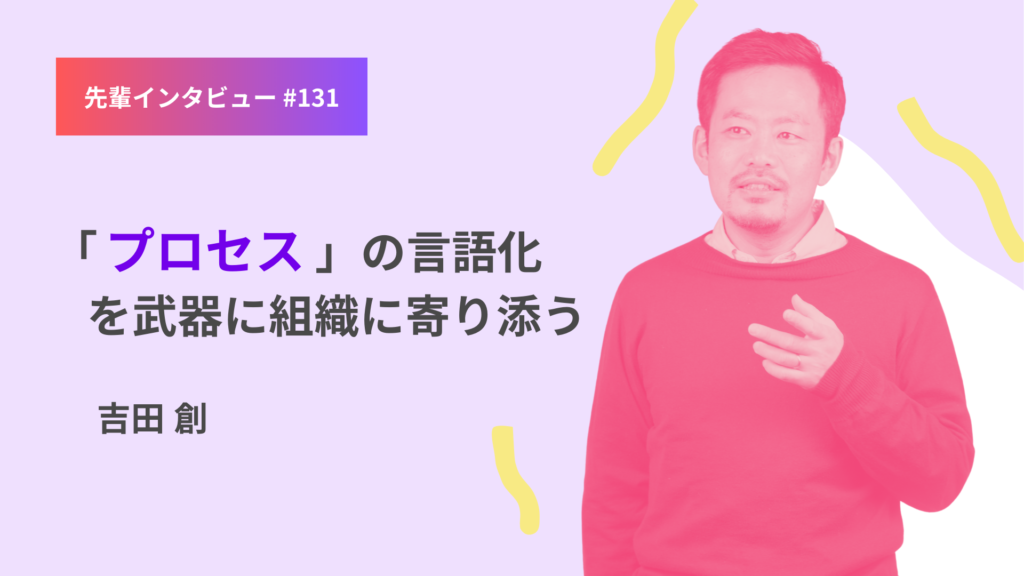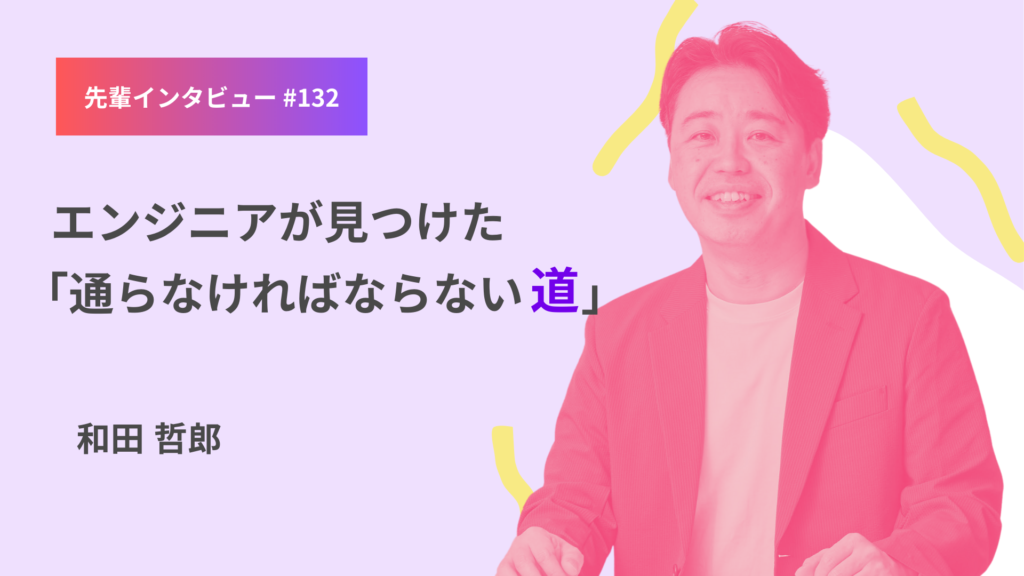
社会人大学院の経験談を紹介する「先輩インタビュー」
今回は、立教大学大学院経営学研究科リーダーシップ開発コース(LDC)在学中の和田 哲郎さんです。
転勤族の家庭に育ち、幼少期から「馴染み方」や「コミュニケーションの仕方」について人間関係の構築を考えてきた和田さん。ITエンジニアとしてのキャリアを積み重ねる中で、「組織と人」への関心を深め、社会人大学院への進学を決意します。大手インターネット企業での開発責任者としての経験、自身の会社経営、そして家庭との両立など、多忙を極める日々の中で見出した学びとは—
新卒で大手電機メーカーに勤務し、その後は大手インターネット企業でエンジニアとして活躍。現在は株式会社NEWONEで開発に携わる傍ら、自身の会社も経営。立教大学大学院経営学研究科リーダーシップ開発コース(以下、LDC)に在籍中。
note : https://note.com/tetsurocks
talentbook : https://www.talent-book.jp/new-one/stories/52578
在学中の大学院:立教大学大学院経営学研究科リーダーシップ開発コース(LDC)在学中
研究内容:MVV(Mission Vision Value)を起点としたプロアクティブ行動の醸成と組織文化変革
入学年月 :2024年4月
修了予定年月:2026年3月
●「コミュニティでの立ち回り方」を模索し続けた少年時代
——まずは和田さんのこれまでの経歴について聞かせてもらえますか。
僕は転勤族の家庭に生まれたので幼い頃から転校を繰り返していました。転勤族として育つと、新しい学校やクラスに馴染まないといけないので、おそらく普通の子供より多くの苦労をしてきたと思います。
コミュニティへの馴染み方やコミュニケーションのとり方については、小学校の頃から無意識に考えていたような気がしますね。
——小さい頃から組織の中での自分の在り方を考えていたんですね。
高校に入る頃は福岡への転勤に伴って、福岡の高校に通っていました。新しい環境に慣れることと、自分らしさを早く出していきたいという思いがあったので、いろんなことにチャレンジしていました。部活や文化祭の実行委員をしながらも勉強との両立に苦労していました。
高校卒業後は大阪で浪人生活を送りました。浪人というのは本当に孤独なんです。早くこの状況から抜け出したいという気持ちが強かったですね。その後、大学に入学しましたが、その孤独を取り戻すかのように、いろんなコミュニティに入って活動していました。大学ではなぜかストイックな体育会のテニス部に入ってしまったのですが、上下関係がめちゃくちゃ厳しい部活だったので大変でした(笑) でもテニス部に所属しながら、大学祭で模擬店を出したりさまざまな業界のバイトを経験しながら、いろんな世界を見たいと思ってアクティブに活動していました。
——そこでも友人関係を築くのに、主体的に行動されていたようですね。
転校を繰り返して培ってきた経験が、大学での友人関係づくりに繋がったと思います。もし普通に小学校、中学校で過ごしていたら、こんな関係性を築ける友達には出会えなかったかもしれません。今でも続く友人関係ができたのは、これまでの経験があったからこそだと思っています。

●向上心が理想のエンジニアに近づかせてくれた
——大学では何を専攻していましたか?
情報工学を専攻していました。主に情報処理の学問だったのですが、漠然といつかは何かしらの開発エンジニアとして仕事がしたいと思っていました。新卒で大手電機メーカーに入社して、消防システム開発の部署に配属されました。どこの消防署にも、119番通報があると通報場所が表示される大画面の消防システムがあるのですが、その開発に携わっていました。
——でも、そこにずっといようとは思わなかったんですね?
はい、消防システムは守りのシステムで新機能をどんどん追加したりはせず、いかに安定運用させるか、に重点を置く開発だったのであまり魅力的ではありませんでした。一方で、その頃は世の中で様々な先進的なWebサービスが登場していた時代だったので、ウェブエンジニアへの憧れがずっとあったんです。社内で部署移動の希望を出して、ようやくウェブ開発ができる部署に異動しました。そこでの仕事は面白かったのですが、内容としては物足りなくて、もっと多くの人に使ってもらえるプロダクト作りに携わりたいという想いが強くなっていきました。
——「このままではやっていけないと思った」とおっしゃっていましたが、それはキャリアの安定性に不安を感じたということですか?
そうですね。自分がやれる範囲が狭くて、これ以上のスキルアップが望めないなというのを感じていました。世の中ではモダンな開発をやっているのに、社内ではレガシーな開発ばかりで、なぜ新しいことにチャレンジしないのだろうと。 残念ながら周りの人はそれほど危機感を持っていないようでした。
——なぜそう思われたんでしょう?漫然と過ごすという選択もあるのに
それは、やはりエンジニアとして成長したいという想いが強かったんだと思います。ウェブエンジニアとしてこういうことができるとか、こういう姿になりたいというのが自分の中では明確にありました。そのような姿に近づくには当時の仕事だけでは絶対になれないという危機感を持っていたからだと思います。
——ウェブエンジニアとしての理想像があった、ということですか?
まさにそうですね。ネットの記事などで第一線で活躍しているエンジニアを見て刺激を受けていましたし、自分もそういったエンジニアになりたいという憧れがありました。 当時は早くスキルアップしなければ、という焦りの気持ちがすごく強かったと思います。
それで、当時まだ規模が小さかったインターネット企業に転職しました。僕が入社した時は社員が300人もいませんでした。エンジニアなんて30人か40人くらいだったと思います。今では考えられないかもしれませんが、会社に泊まって仕事をすることもありましたね。でも、そこで本格的にウェブ開発ができるようになって、満足していました。本格的なウェブ開発エンジニアとしてのキャリアはその頃からだと思っています。
——すごく充実していたんですね。そこからどんな経緯で組織開発に興味を?
入社して約5年くらいは現場でひたすら開発をしていて、その後、プレイングマネージャーのような立場になって、新規サービスをどんどん立ち上げていきました。様々なサービスを掛け持ちでマネジメントしたり、エンジニアとして手を動かして開発したりしていました。希望していたことをがっつり任せてもらえたので、満足度は高かったと思います。
それからさらに5〜6年経った頃に、開発部長という役職についたんです。70人くらいのメンバーをマネジメントすることになりました。それまでの仕事とは違って、エンジニア一人一人の成長をどう促すかということを考えないといけない日々でした。それまでガリガリと手を動かしていたのに、急にそういう立場になると、いろんなことを考えるようになって。多分その頃から、エンジニア組織における人材開発や組織開発に興味を持ち始めたと思います。
——組織を変えることの難しさを実感されたんですね。
おっしゃる通りで、組織を変えるとか動かすというのは全然うまくいかないなと思いました。
その会社を辞める前から副業のような形で株式会社NEWONEに関わることになりました。一方で自分で会社を立ち上げて、ある企業の開発顧問として入ったり、これから開発組織を作っていきたいというところに入って、一緒に開発組織を構築する仕事を自分の会社でやっていました。今も自分の会社をやりながら株式会社NEWONEにも関わっています。
●人と組織に向き合うエンジニア
——人材開発や組織開発に興味を持ち始めたということですが、具体的にはどのようなきっかけがあったんですか?
エンジニアという職種は好きなんですが、ずっと気がかりなことがありました。
それは、エンジニア組織って「人と組織」にしっかり向き合うことの大切さをないがしろにしている部分があるんじゃないか、ということをずっと働きながら思っていたんです。なんか物作りだけしていればいいみたいな感覚の人が多いなという印象がありました。職人気質の人が多いので当然と言えば当然かも知れませんが、いつかどこかで限界が来るだろうなと。
その頃、僕はアジャイル開発のスクラムという手法を導入していたんですが、スクラムは人とか組織を重視する考えで開発を進めていくんです。その思想に共感していて、認定スクラムマスターという資格も取りました。でも、もっと専門的に「人と組織」というところに向き合っていきたい、探求したいという思いが強くなっていったんです。

——それで社会人大学院を考えるようになったんですね。
はい、エンジニア組織の課題感をすごく感じていたので、自分自身がやっていることや現場での取り組みが、その場しのぎでやっているようなものになっちゃっているんじゃないかという疑いもありました。人材開発や組織開発について少しずつ知るようになってきて、だんだんと立教大学大学院の中原淳先生に行き着くんですよね(笑)調べていると、よく出てくるんです。
——それで大学院進学は通らなくてはいけない道なんじゃないかと思ったんですね?
それまで人材開発とか組織開発という言葉も知らなかったんです。でも、素人ながらにも「この道を通るしかない」と思いました。
2022年にLDCの存在を知って、2024年に入学することになりました。近年は倍率が非常に高くて、ちょっとした狭き門ですよね。入学希望者が増えないようにサイトとかで宣伝しないでくださいって思っていました(笑)
●大学院で気づいた「対話の重要性と学びのスタイル」
——大学院での学びや、意外だったことについて教えてください。
学びはやはり、ただ受け身で講義を聞くのではなくて、グループワークだったり、理論についての議論が必ず設定されていて、自分たちで学びを作り上げるという感覚があるんです。教授はあくまでもきっかけを与えてくださる存在で、学びをどう深めていくかは僕たち次第なんだなというのをすごく感じています。
そういうことを分かっているからこそ、グループワークや議論は真剣に取り組む雰囲気になっていて、いつも刺激を受ける場になっていると思います。
——同期との関係性はいかがですか?
入学した時、みんなのレベルの高さに圧倒されて「もしかして自分は場違いなところに来たのかな?」みたいな感じはありましたよ(笑)。でもそういうのを感じても、なぜ自分はLDCに入学したいと思ったのか?という初心を思い出しながら取り組んでいます。大変な分、大きく成長できる環境だと思います。
特に印象深いのは、1年次春に実施するグループワークのLWP(リーダーシップ・ウェルカム・プログラム)ですね。ちょっとしんどい時期がありました。みんなと比べてしまって自分を責めたりしましたが、そういう想いをLWPの仲間同志で最後に吐露する場があったんです。そこで仲間からのフィードバックをもらって自分の気持ちが浄化されたような気がしました。
——議論の中で、詰められているような感じを受けることもあったんですか?
はい、グループでは議論の質をさらによくするために質問してくれたり聞いたりしてくれるのですが、人によっては詰められているように受け取るかもしれません。自分はそういったことに最初は慣れていなくて。俯瞰して「より良くするにはどうすればいいか」を考える視点が、当時の自分にはまだ十分に備わっていなかったんです。その感覚が最近は分かってきたので、いまの感覚でLWPをやっていたら辛いとは思わなかったかもしれません(笑)
——批判的思考に慣れるというところが良かったんですね。
そうですね。エンジニアの世界でも批判的思考は必要なんですが、エンジニアの現場では自分が言われるのではなくて、言う方なんです。「こういう実装だったらこんなリスクがあるから、もうちょっと考えた方がいいよね」とか「事故につながるよね」というようなことを言わないといけない。でもLDCでは違って、自分自身が言われる立場になるんです。
●学びをエンジニア組織の現場に持ち帰る
——大学院での学びは、エンジニア組織でどのように活かせそうですか?
これは自分で気づいていなかったことなんですが、物事を解決させるときにある程度僕が答えを出してしまうことが多かったと思うんです。でもそうじゃなくて、ちゃんとみんなに考えてもらって、みんなが自分で判断ができるようになることを意識して問いかけをしないといけなかったなというのが、反省点としてあります。
そこに至るまでは単なる問いかけじゃなくて、対話が必要だと思うんです。エンジニア同士はすぐ答えを出したがる傾向があるので、いろんな人の意見や反対意見を聞きながら、チームとしての最適解は何なのかを話し合う場を作るのが僕の役割なんじゃないかなと考えるようになりました。
——効率を重視しがちなエンジニアの文化に対して、新しい視点を持ち込むということですね。
そうなんです。どうしても近道を探してしまうんです。エンジニアって無駄なことが嫌いで、すぐに効率化とかに目が行きがちなんです。でもそれが求められる職種ではあるんですが、その水準を追求するためには一時的に非効率に見えることもやらないといけないんですよね。立ち止まって話さないと見えてこないことってたくさんあるということを実感しています。
●進学を考える人へのアドバイス
——大学院進学を考えている人へのアドバイスはありますか?
LDCに入った後に何を学んでどう生かしていきたいかというのを明確にしておくといいんじゃないかなと思います。目的意識がはっきりしていないと授業も受け身になっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。あとは入ったら何とかなります(笑)。周りの同期が自分より優秀に見えてしまうのはみんな一緒だと思うので、日和らずに、なぜここ(LDC)に来たのか?をいつも心に持っていると良いと思います。
——進学前に準備しておくべきことはありますか?
難しいかもしれないですが、論文を読むトレーニングはやっておくといいかもしれないですね。全部読む必要はないんですが、事前に少しでも読解力を鍛えておくと良いのかなと思います。僕も論文を読まないといけないと言われてから読み始めたんですが、最初は全然読めなかったんです。でも興味のある論文を探していると、だんだん自分の中の地図が広がっていくような感覚になってきて。
RPGゲームのように少しずつマップが広がって活動できる範囲が増えていくようになるよ、ということをLDCの先輩から教えてもらったんですが、そういう感覚が分かるようになってきました。興味のあるものをちょっとでも読んでおくといいのかなと思います。
——仕事と学業との両立はいかがですか?
仕事と学業の両立は大変でしたが、なんとかなりました(笑)。 加えて今年は息子の中学受験があったのですが、お風呂の中で彼と対話をしながら少し先の未来の話をしてみたりして本人のモチベーション維持に関してはしっかりフォローすることができたと思います。
——進学の費用面でのアドバイスはありますか?
私は自分で事業をしており、教育訓練給付金を使えないので完全に自腹でした。でも返還不要の奨学金が大学にあるので、それが一つの選択肢としてありますね。
●次の一年へ向けて
——最後に、次の一年に向けての抱負や期待を教えてください。
修士論文にあたるLFP(リーダーシップ・ファイナル・プロジェクト)では、これまでグループワークで取り組んできた組織介入の続きを私一人で行うことになるので、しっかりと取り組みたいと思っています。引き続きメンバーや現場の人たちとの対話を大切にしながら、より良い組織づくりに貢献していきたいです。
何より、これまで気づかなかった視点や考え方を学ぶことで、エンジニア組織のリーダーシップのあり方について新たな知見を得て、それを実践に活かしていきたいと思います。まだまだ学びの途中ですが、一歩一歩前進していきたいです。
——今日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。和田さんの経験が、社会人大学院を考えている方々の参考になると思います。
こちらこそありがとうございました。少しでも誰かの参考になれば嬉しいです。
実は僕はLDCに入る前から、このElephant Careerの先輩インタビューを見させていただいていたんです。個人的にとても勉強になりましたし、すごく刺激をもらいながら「やっぱりLDCに入りたい」と思っていました。自分のインタビューが誰かのためになれば嬉しいなと思っています!
——読んでいただいていたんですね!ありがとうございます!