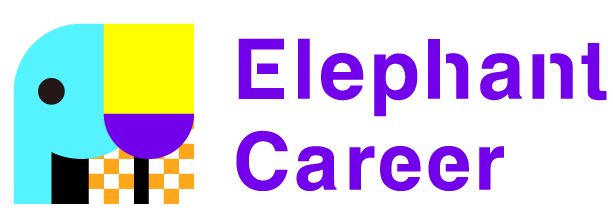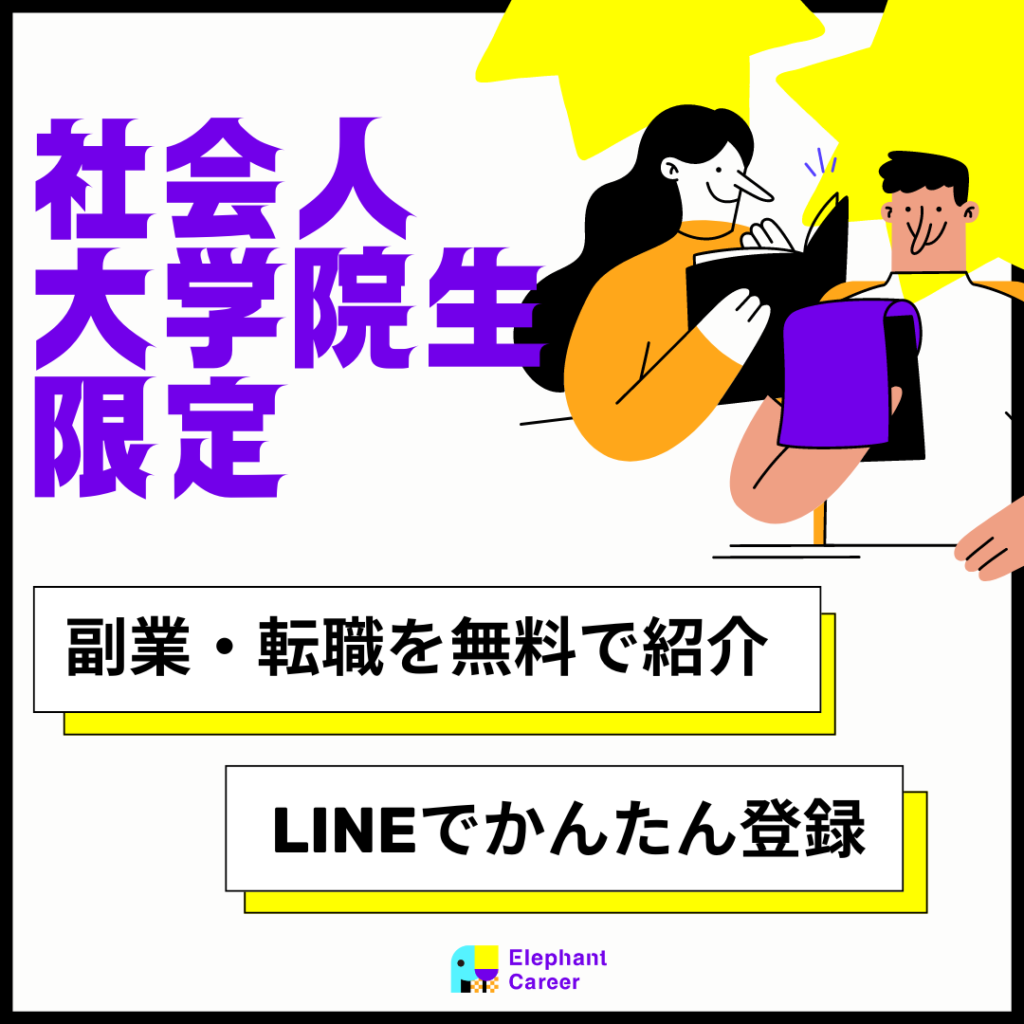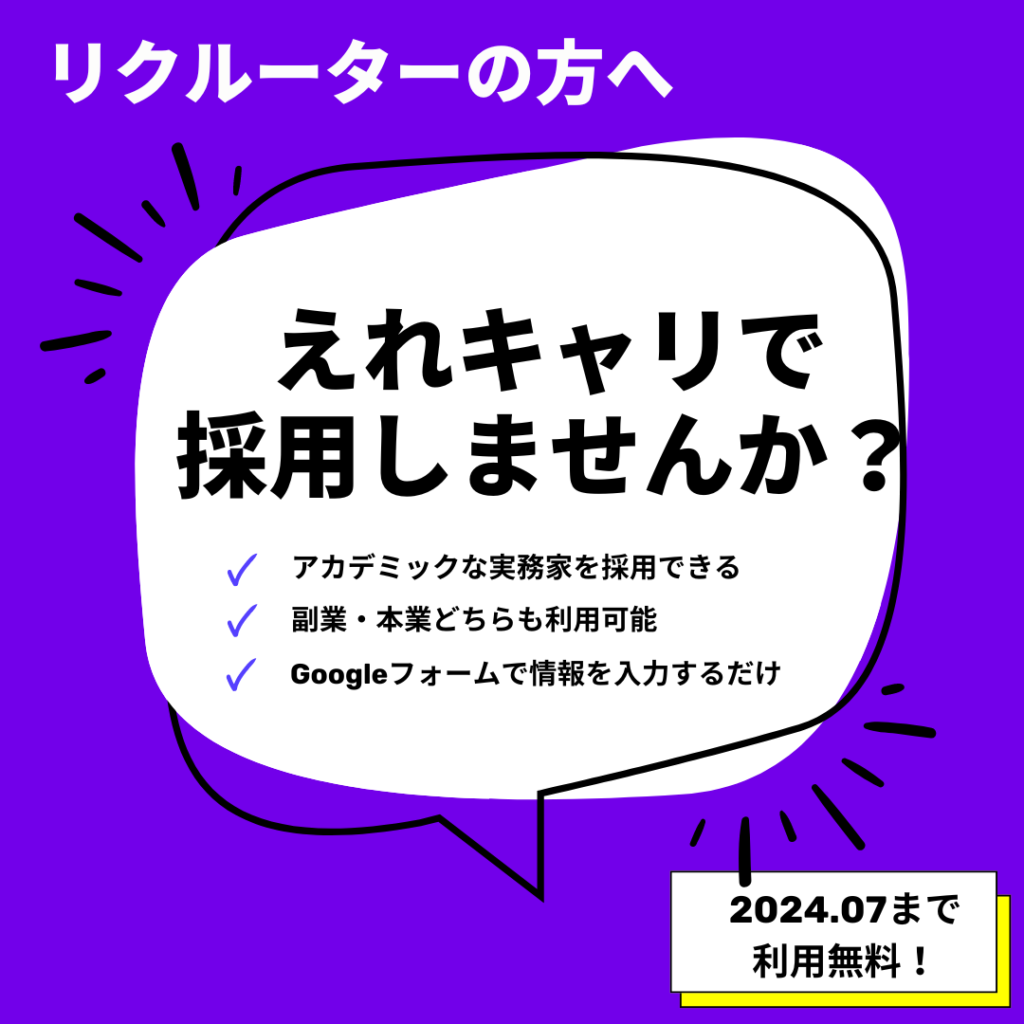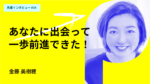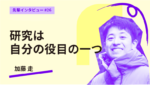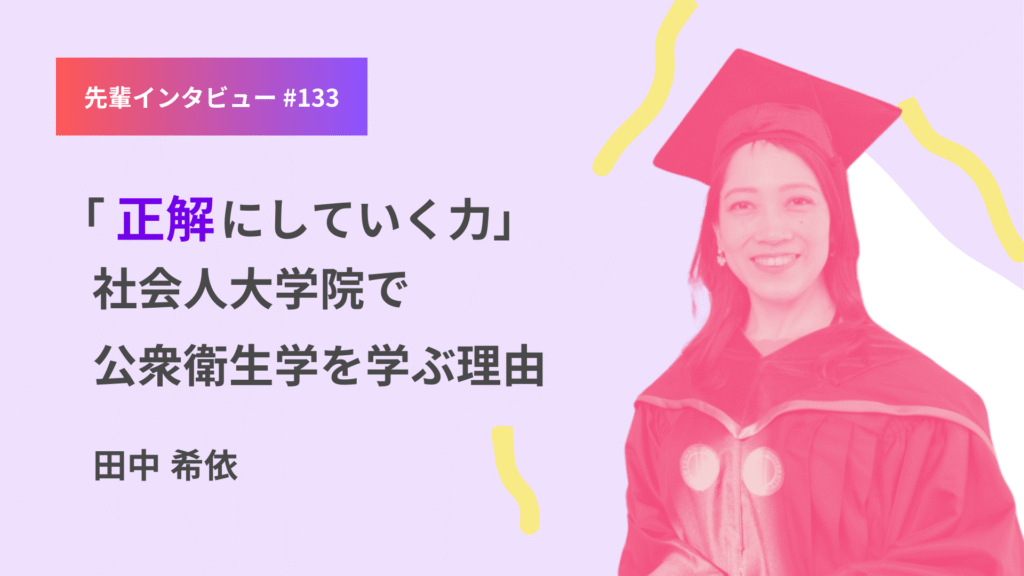
社会人大学院の経験談を紹介する「先輩インタビュー」
今回は、順天堂大学大学院医学研究科(博士課程)在学中の田中 希依さんです。
MR(医薬情報担当者)、メディカルライターを経て、現在は外資系体外診断用医薬品メーカーで臨床開発や企業のSDGs活動に携わる田中さん。これまでのキャリアの中で、法学部出身というバックグラウンドを強みに変え、医療業界でご自身のポジションを確立されてきました。そして現在、順天堂大学大学院で公衆衛生学を学びながら、次のステップに向けて準備を進めています。
社会人大学院への進学を考えている方に向けて、田中さんの経験や考え方を余すところなくお届けします!
同志社大学法学部法律学科卒業。製薬会社のMR、メディカルライターを経て、現在は外資系体外診断用医薬品メーカーで臨床開発とSDGs関連業務に従事。2025年3月順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学専攻修士課程修了。2025年4月より同大学院博士課程に進学。
在学中の大学院:順天堂大学大学院医学研究科(博士課程)在学中
研究内容:生活習慣病等の疾患や不眠症状と社会的要因との関連
入学年月:2025年4月
●「キャリアの始まり ― MRという選択
——まずはここまでの仕事のキャリアについて教えていただけますか?
大学時代は法学部法律学科で勉強していて、知的財産法という著作権や特許、商標、意匠法などを扱うゼミに所属していました。就職活動を経て製薬会社でいわゆるMRとしてキャリアをスタートしました。
実は最初からMRがしたかったという強い気持ちがあったわけではなくて、リーマンショック翌年だったこともあり、就職が無理だったら大学院に行こうかなという気持ちもあったんですよ。ですが当時は大学院の学費が出せなかったし、早めに独り立ちしたいなということもあり、そのまま就職しました。
ただ、その時から、就職しても大学院にもう一度行きたいなと思ったらいけるよね、というのはどこかで思っていたのかもしれません。
——時代の影響を受けて、MRという仕事にたどり着いたんですね。
就職の集団説明会って、いろんな企業が一堂に会していますよね。そこに片っ端から行ったんですよ。自分の肌に合いそうなところに申し込んで、たまたま最終面接を通過して内定が出たのがMRでした。
——色々と情報収集する中でご縁があったという感じですか?
そうですね。なんか正解を探すというよりも自分で選びとった道を正解にしていくのがキャリアなのかなって(笑)
実は、MRになった時に周りからは「向いていない」って言われたんです。家族からも友達からも「絶対お前には向いていない」って。
——そうだったんですか!
でも受かっちゃったので、とりあえず行ってみようかなと思って。
MRは最初の半年くらいに泊まり込みで勉強しなきゃいけないんですが、座学だけじゃなくてプレゼンやコミュニケーション方法などを徹底的に叩き込まれました。あまりコミュニケーションが得意な方ではなかったんですが、今考えるとその時の経験がその後も自分の身を助けてくれているなと感じています。
お医者さんはMRに説得されて薬を買いたくないんだから、自分で納得して自社製品を使おうと決断して貰えるようにしなさいと言われて、うまく提案する方法などを学びました。
——すごいですね。お医者さんに「確かにそれはいい薬だね」と言わせるんですね
そうですね(笑)まあ、普通に考えても無理です(笑)
●転機 ― MRからメディカルライターへ
——2社目に転職されたのは何かきっかけがあったんですか?
2年半現場で働いてみてMRは自分には向いていないなと思ったんです。売上げを追われるのが本当に苦手で。患者様の病気が良くなることで薬が売れなくなって売上が落ちたら評価がマイナスになってしまうってなんかおかしな世界だなと思ったんです。
転職することで年収が下がるのは怖かったですが、一時的に下がったとしても専門知識をつけて、できる人が限られてる仕事に就きたいと考えるようになりました。そんな矢先にメディカルライターの仕事が見つかったんです。
——メディカルライターとはどんなお仕事ですか?
どれも医療の専門知識を活かした仕事なんですが、大きく三種類あるんです。製薬会社の申請書類を作ったりするケース、製薬会社の顧客向け資材を作成するケース、一般向けに医療に関わる情報を発信する仕事です。私がしていたのは二つ目で、具体的にはインタビューフォームや「くすりのしおり」、販促資材などを作成していました。
薬剤師の方が採用されることが多いのですが、たまたま学歴不問で、MRのバックグラウンドを持つ人が欲しいということで募集があり、転職できたんです。入社後に分かったんですが、その部署が薬剤師ばかりで、MRの現場知識がある人が居なかったから、ご縁があったようです。
おもしろいのが、製薬企業から受注した資料を作っていく中で著作権処理が必要になるんですが、それがちょうど学部での知的財産法ゼミで学んだ知識と結びついたんです!一緒に働く人は誰もその知識がないので、私が持つ法律のバックグラウンドの知識が役立ちました。
——領域を越えるからこそ生まれる価値ですね。越境人材だからこそ出る価値!
そうなんですよ。医療系の業界では、医師や薬剤師、博士号を持っている人、MBAを持っている人、公衆衛生学の修士を持っている人など、スキルを持っている人が多くいて、その人たちと戦うことになるんですが、全く違う武器を持つことで、自分のポジションを作ることができるんだなと実感しました。
——掛け合わせの強み!一つのことを突き詰めるだけではないキャリアの作り方ですね!

●現在のキャリアと社会人大学院への思い
——メディカルライターはどのくらい続けたんですか?
4年弱です。そこで飽きたなと思ったんですよね。企業から言われたことを言われた範囲内でやる仕事だったので、あまりクリエイティブさがなくて。何かを生み出す仕事がしたいと考えて、今の体外診断用医薬品という、病気の診断用の製品を作っている会社に移りました。
——今のお仕事はどのくらいされているんですか?
もう7年くらいです。今までのキャリアで1番長くなりました。
——どんなことをされているんですか?
かなり幅広いことをしていますが、1番分かりやすいのは臨床開発です。本社が海外にあるんですが、海外で開発した製品を日本で医療用として発売するためには、厚生労働省から承認を取得する必要があります。厚生労働省に申請を出すためのデータ取りのための臨床研究を実施したり、保険診療にするか自費診療にするかの検討、学会のガイドラインに載せてもらうための活動、実際に現場で使ってもらうための講演会やセミナーの開催、さらに具体的にどのような使い方ができるのかアンメットメディカルニーズを探索する臨床研究も行っています。
他にも、サブの仕事として、本社が力を入れているSDGsに関連して新しくできた部署でも働いています。、そこでは、職場の衛生管理や安全管理、従業員のウェルビーイング、CO2削減のための活動などをしていますね。
——すごい!2人分働いてますね。それだけ信頼されているということですね。それと周りから声がかかった時にそれを掴み取っていく力が田中さんは高い方だと感じます。だからいろんなものを手繰り寄せて活躍されているんですね。
昔からやらない後悔よりやる後悔の方がマシだなって、ずっと思っているので。やってみて無理だなってやめることはできるけど、やらずにあとでやっぱりやっといた方が良かったかなって思うのとでは後悔の仕方が違うなぁと。
——大学院はいつから考えるようになったんですか?
1社目の時にも大学の薬学部に行き直そうかなと思ったんですが、薬学部って6年かかるのがネックでしたし、薬剤師免許が欲しいというわけではなかったので、進学しなかったんです。
その後、今の会社に入って半年後に3ヶ月間シンガポールのプロジェクトにアサインされたんですが、そこでは周りが全員ドクターだったんです。そこで「君の学歴は?」と聞かれた時に「法学部の学部卒だよ」と言うと「何だと」みたいな反応で(笑)
その時に海外で戦うためには、PhDは必須だなと思ったんです。
●進学先の選択と決断
——大学院に行こうと思った時、どのように専攻を選びましたか?
PhDを取るというのは相当きついと聞いてましたし、論文も書かなければならないので、研究分野によっては自分が飽きてしまうんじゃないかという懸念もありました。
医学系の大学院でも、様々な専攻があります。遺伝子や細胞レベルの基礎研究とか、薬剤の治療効果があるかを検討する臨床試験とか、数ある要素から疾患のリスク因子を探し出す疫学研究とか。私は飽きやすいタイプの人間なのでタンパク質を研究する、みたいな分野には飽きが来るだろうと思いました(笑) それから、婦人科や循環器科などの疾患領域別の研究も、私の職場では担当領域がコロコロ変わるので、潰しが利かないと思いました。そうやって色々調べる中で、専攻は公衆衛生学が一番自分に合いそうだとたどり着きましたね。
——大学はどのように選びましたか?
日本の大学院に社会人として通うパターン、会社を休職して留学するパターン、あと会社の中で海外転勤をして現地で働きながら転勤先の大学で学ぶパターンなどいくつかのシナリオを考えました。
最終的に日本の大学院に社会人として通うパターンを選びました。私は文系出身なので入試に数学や化学、生物がなくて、面接と英語だけで受けられる大学を探していたところ、見つけたのが順天堂大学でした。学費も国公立並みに安かったんです。さらに、今の会社に入社した時の部門長が、順天堂大学で社会人博士を取ったという話を聞いていたので。事前に行きたい研究室の教授にコンタクトを取って話を伺いました。そこで行きたいなと思って、上司に相談したら、「承諾書を書いてあげるから申し込んだら良いよ」と言われて、そこから修士に進学しました。
——今は修士何年目ですか?
今は2年目で、今年修了して、今年の4月から博士課程に進む予定です。同期は5人いて、そのうち3人が社会人学生です。あとはバイトしながら看護師をしている留学生とフルタイムの学生です。
●社会人大学院での学び
——研究はいかがですか?面白いですか?
今まで仕事やっていたことが明確に整理される感覚がとても面白いです。やはり社会人経験があるだけでなく、医療業界と法律、SDGsなど様々な分野の経験があることで、授業の理解度が全然違うと感じることがよくあります。
——社会人経験が学びを深めるんですね。
そうなんです。例えば、SDGs関連の講義でも既に会社で関わっているので「知ってる知ってる!」みたいな場面が多いです。会社の労働衛生や従業員のストレスチェックなども、実施した経験があるからこそわかるものが多いです。
やはり経験したからこそ分かるというのは大きなアドバンテージです。働きながら時間を作るのは大変ですが、課題やレポートが出された時は、自分の仕事上の経験を紐付けて書き進めることができるので、社会人経験のないフルタイムの学生さんと比べると、何を書くか、みたいな悩みが少ないと感じました。
——学びの面白さはどこにありますか?
全部です(笑)新たに生じる疑問について先生とディスカッションできるのも楽しいです。ディスカッションの内容が結構ハイレベルなので、先生も楽しそうなんですよね。あと、仕事で褒められることはあまりないけれど、大学では褒めてくれる人が多いので、「意外とできるじゃん!」と発見があるのも嬉しいです。
●苦労と乗り越え方
——大変だったことや意外だったことはありますか?
順天堂大学は社会人学生大歓迎!というスタンスですが、研究室によっては社会人学生にフルタイム学生レベルのコミットを求めてくるところもあります。絶対に日中に対面講義を受けなきゃダメとか言われたりすることもあります。
だから、OBやOGから、具体的にどんな感じなのかを聞くのが大事です。実態をちゃんと確認しておくと、有休の使い方などを調整して、計画的に動くことができると思います。
——進学前にもっと準備しておけばよかったなということはありますか?
もう少し早めに入っていたかったなと思うことはあります。コロナ中だったら楽だったかも、というのと、やはり体力がある若いうちの方が仕事にも学生生活にもフルコミットしやすかったかな、と。体力がないと、どちらかが不満足な結果になってしまうと思うので。
まあでも20代だとちょっと早い気もしますし、ある程度の経験を重ねて、それを活かすこと、体力や頭の柔軟さの面も併せて考えると、30代に進学するのがちょうどいいのかなとは思います。
——仕事との両立はどうしていますか?
会社がテレワークできる環境なので、夕方どうしても大学に行かなければならない時は在宅勤務したりしています。また、大学の先生も理解してくれる方が多いので、事前に計画を立てて会社にも大学にも話を通しておけば融通が利くことが多いです。
●これから学びを検討する人へのメッセージ
——最後に、社会人大学院への進学を考えている人へのアドバイスをお願いします。
まず、「やってみる」という姿勢が大事だと思います。事前に全ての準備が整わなくても、一歩踏み出してみることで見えてくるものがたくさんあります。私も最初は不安でしたが、実際に始めてみると思いがけない発見や成長がありました。
それから、無理だったら休学するという選択肢も常に持っておくことです。学費が高額でもったいないと思うかもしれませんが、自分の成長への投資と考えれば価値はあります。
あとは、自分の経験を活かせる専門分野を選ぶことも重要です。私の場合は、法律、医療、海外勤務という異なる経験が公衆衛生学で活きました。あなたの経験や強みが何か、それをどう活かせるかを考えてみてください。
最後に、体力と時間管理は本当に大事です。社会人大学院は大変な分だけ得られるものも大きいので、チャレンジする価値は十分にあると思います。
——貴重なお話をありがとうございました。田中さんの経験が、社会人大学院を検討している方々の参考になると思います。