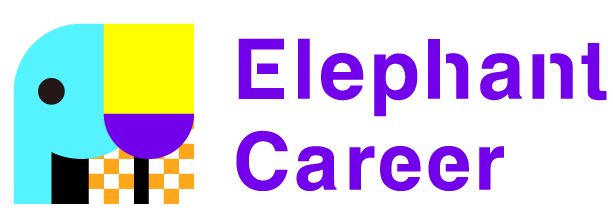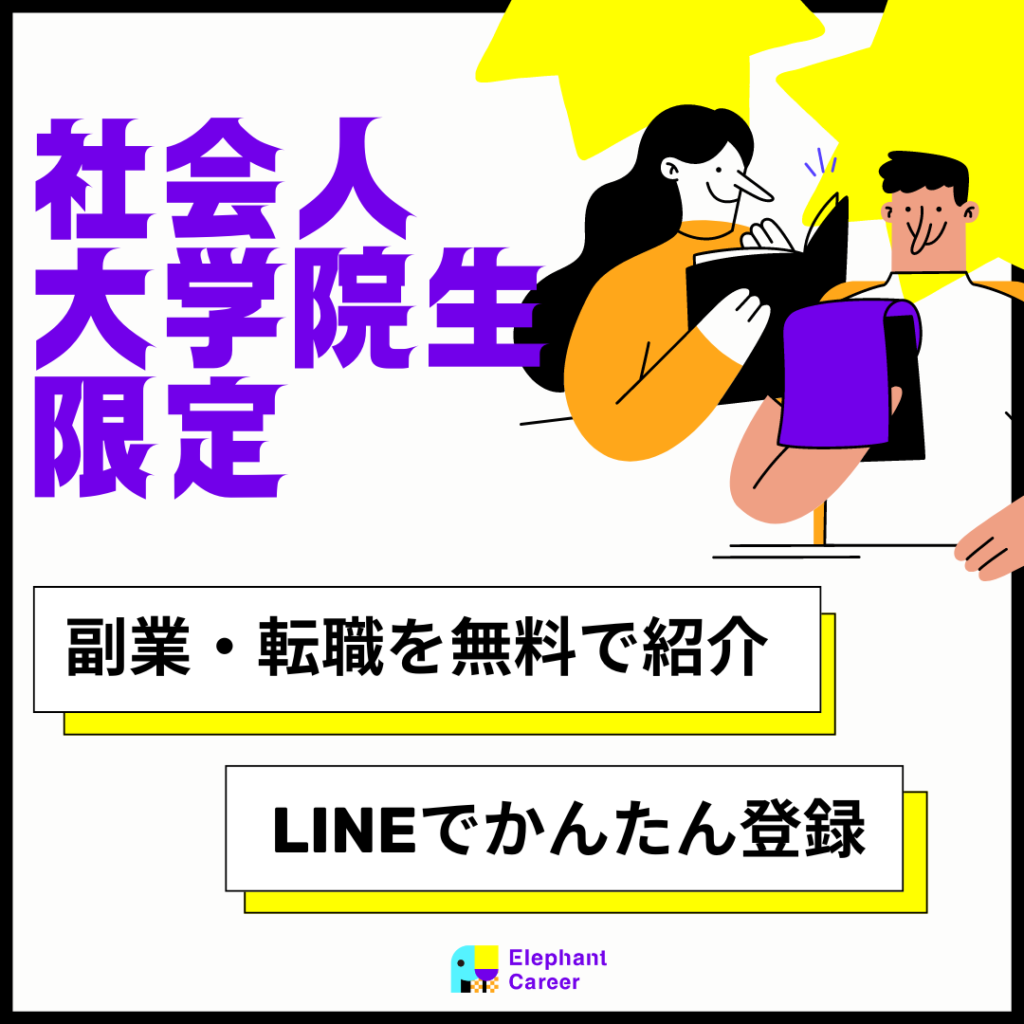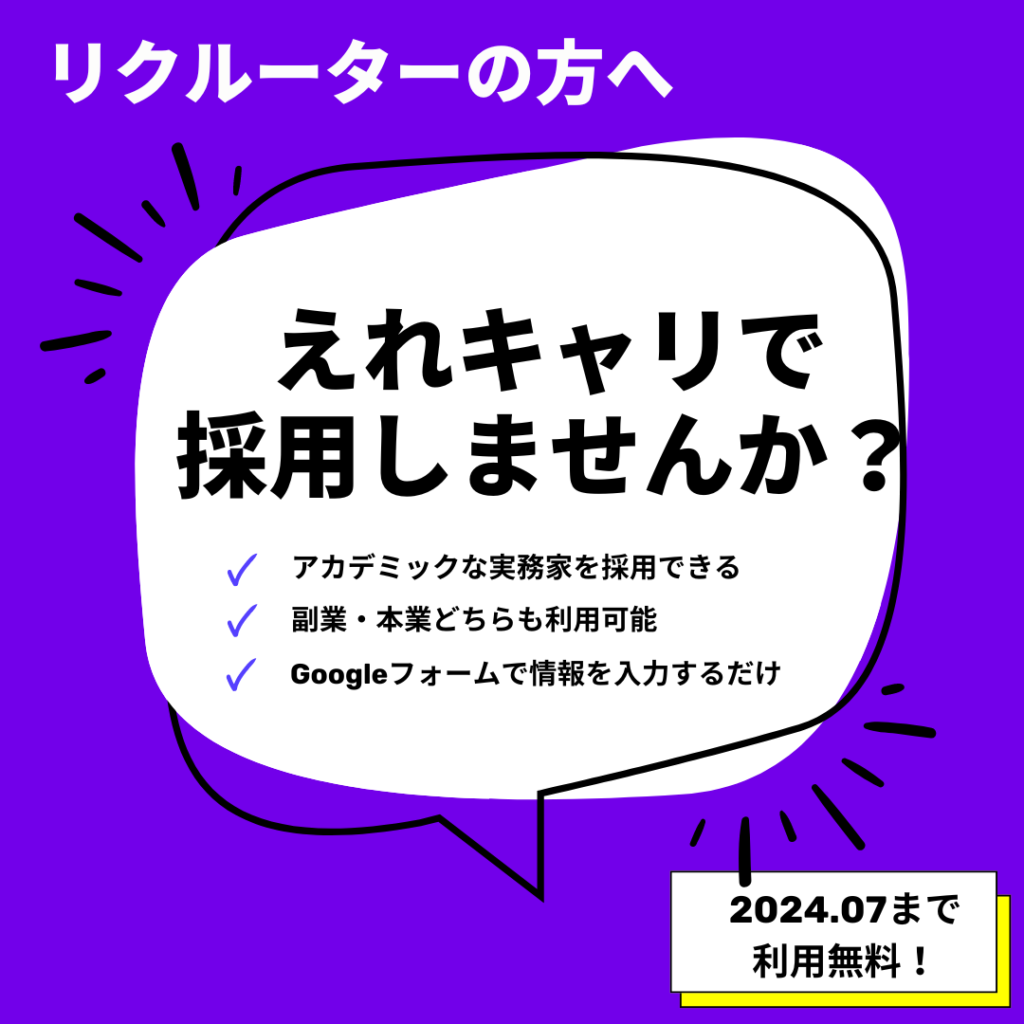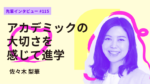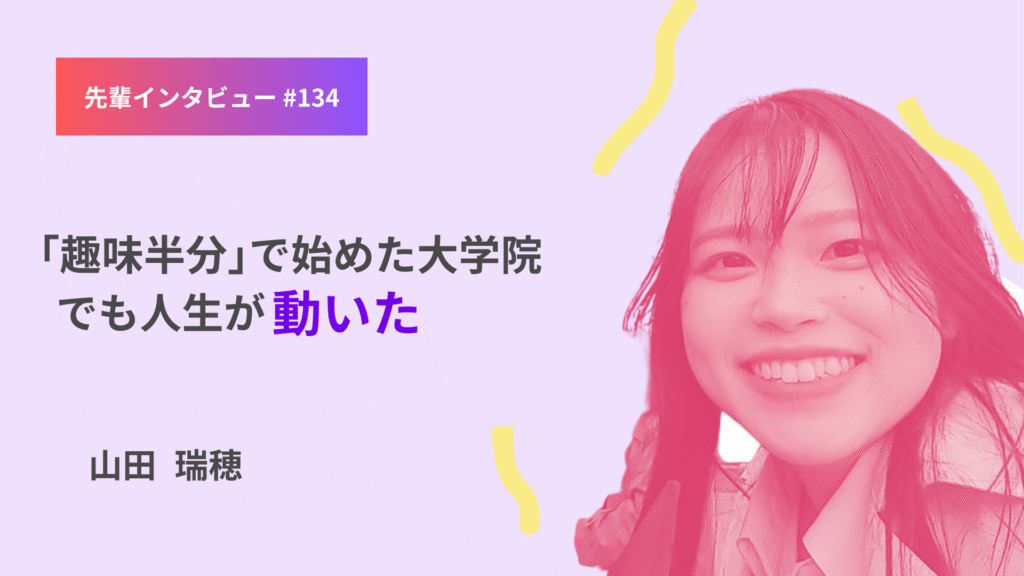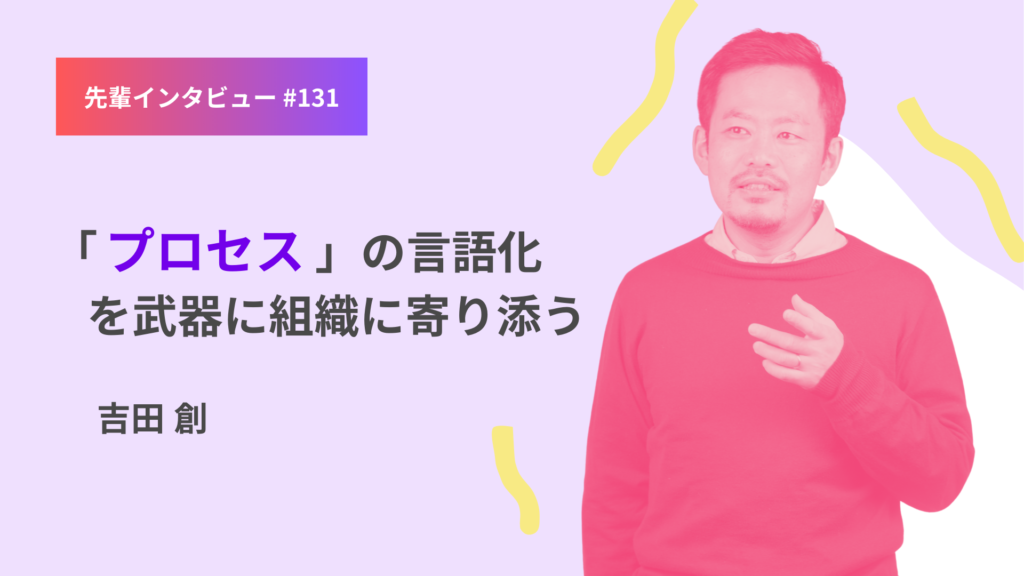
社会人大学院の経験談を紹介する「先輩インタビュー」
今回は、立教大学大学院経営学研究科リーダーシップ開発コース(LDC)在学中の吉田 創さんです。
吉田 創さんは、現在50歳。社会人大学院で組織開発を学んでいる。アメリカでの古着ビジネスから始まり、IT企業の経営、そして組織開発のコンサルタントと、常に新しいことに挑戦し続けてきた。今回は、なぜ50歳という節目に社会人大学院への進学を決意したのか、その背景にある思いや経験について語っていただきました。
18歳で渡米し、アメリカでアパレルの貿易事業を起業。多民族・多文化の環境下、特にユダヤ系バイヤーとのネゴシエーションを通じて、交渉力と国際的なビジネス感覚を磨く。帰国後はIT領域で音声認識技術を活用した世界初の社内コミュニケーションシステムを開発。通信キャリアへの新規事業支援、複数のM&A/バイアウト/MBOに関わるなど、経営実務全般を経験。
2009年より人と組織の可能性に焦点をあて、人材開発・組織開発の分野へと転身。企業研修、経営合宿、組織文化変革など、多様な現場で実践と支援を行っている。
https://www.yoshida.so/index.html
在学中の大学院:立教大学大学院経営学研究科リーダーシップ開発コース(LDC)在学中
入学年月 :2024年4月
修了予定年月:2026年3月
●未来を見据えた選択の連続
——— まずは高校生の頃からのお話を伺えますか?
田舎の私立中高一貫校に通っていました。推薦で行ける大学がある程度決まっていて、自分の成績であればどこそこへ行けるという将来が見えすぎてしまったのです。それで急にその学校にいることがつまらなくなってしまって。
——— 見えすぎる未来に違和感を感じたのですね。
結局地元の公立高校を受験し直しました。入学してからはめっちゃくちゃ楽しくて勉強以外のことばかりしていましたね(笑)おかげで成績は下から数えた方が早いくらいでした。ただ、ここでも「このくらい勉強したらこのくらいの大学にいけるだろう」と予想できたら、また将来が面白くなくなってきちゃって(笑)
高校3年の途中からアメリカに留学しました。テネシー州の本当に田舎で、片道1時間15分スクールバスに乗って学校に通う生活でした。田舎すぎてしまい、今度は大都会のロサンゼルスのコミュニティカレッジに進学しました。
そこで思わぬビジネスチャンスに出会うことになります。
——— 古着ビジネスでしたっけ?
当時、日本でアメカジブームが起きていて、古着の需要が高まっていたのです。最初は日本の知り合いから「商品を見つけてほしい」とお願いされ、古着を集めて送る仕事から始めました。古着のTシャツを1枚1ドルで仕入れて5ドルで売るような商売です。アメリカのアパレルビジネスはたくさんのユダヤ人が関わっていて、彼らと交渉して買い付けます。セント単位で交渉を重ね、日本の商社を挟んでリスクヘッジをしたり。最終的には1シーズン20万枚のTシャツを扱う規模になりました。一日動くだけで千ドル単位を稼げるので、もう勉強が馬鹿馬鹿しくなってビジネスにシフトし、ビザも学生ビザから投資家ビザに切り替えて大学にも行かなくなってしまいました。そのビジネスは6年間やっていました。
——— 投資家ビザ!冒頭5分での衝撃がすごいです
●IT企業経営への転換
——— そこからITの世界に入られたと伺っていますが、そのきっかけは?
アパレルビジネスも中国製品にシフトしていき、ビジネスの先行きが見えにくくなってきたころ、ちょうどITバブルが始まった時期でもあったのです。「ITでアジアで何かできないかな」と考えていた時に、シンガポール進出を目指す日本のベンチャー企業と出会いました。23歳で帰国し音声認識・音声合成のシステムの仕事に関わることになります。
今でこそ当たり前の技術ですが、当時はまだまだ発展途上でした。3年ほど働いた後、2000年当時26歳独立しました。Unified Messaging Systemといって、メールとボイスメール、電話、チャットを統合するようなシステムを手がけていました。今でいうSlackの走りみたいなものですね。5000万ほど投資を受けて始めたのですが...
——— 何があったのですか
ITバブルが崩壊しつつある時期で、次の資金調達に失敗し、結果的に自分の会社を売却することになったのです。ただ、売却先のオペレーションがあまりうまくいっていなかったので、そこの代表取締役も兼任することになりました。資本金が5億ほどあって、社員が30人ほどいた時期もあります。でも、株主との方向性の違いがあり、自分自身が経営者として至らなかった部分もあって、兼任していた代表取締役を辞任しました。自分で立ち上げた会社は買い戻して、創業メンバーと再スタートしたのです。
当時は自分たちが担いでいたIBMの技術で商用化サービスを立ち上げたのが、世界初だったこともあって、IBMのバイスプレジデントが小さな事務所の当社を訪ねて来たり、香港の企業が買収提案してきたりしと、刺激的で面白かったですよ(笑)
——— へー!吉田さんってなんかいつも一歩二歩早いですよね。時代の先端を行っているような。
新しい物好きみたいなところもあるんですけど、会社を大きくする経営は向いていなかったと今でも思うところです。再スタート後は少人数がとても気楽で、ビジネス自体もすごく上手くいっていました。
●組織開発の扉が開かれる
———2008年にリーマンショックが起きましたよね。
皮肉なことにリーマンショックが起きた9月の売上が過去最高でした。そこからは本当にダダ下がり。クライアントも事業撤退を決めていく中で、自分たちも新しい道を模索していました。そんな時に行きつけのスナックの常連さんに「うちのセミナーに来ないか」と誘われて参加してみました。
———怪しい匂いしかしないですね。
はい。スナックと言ってもカラオケもない、おじいちゃんたちが好き放題喋っているような場所で......ちょっと怪しいですよね(笑)
当時の僕は、いわゆる経験学習も知らなくて、知識伝達型しかイメージになかったのです。もしくはほふく前進をさせられるような体育会系の研修です。このセミナーに参加してみると、それまで全く経験したことがない内容でした。Tグループに影響を受けたアプローチで、とても自己理解が深まり、これがキャリアトランジションの大きなきっかけになりました。
※Tグループ:「トレーニンググループ」の略で、自己理解や他者理解、リーダーシップといった人間関係に関する気付きを得るための学習方法。組織開発の源流とも言われている。
———その「気づき」について、もう少し詳しく教えてください。
それまでの私は、コンテントの世界でしか生きていなかったのです。つまり、「だれが何をしている」という起きていることばかりに注目していました。このセミナーの中で「なぜそれをしているのか?」というプロセスの認知が大事だと気づきました。そこで初めて、自分の在り方や、人との関わり方について深く考えるようになりました。
———強く印象に残っているエピソードはありますか?
そのセミナーには3年間で30回ほど参加しました。初めて参加した時に、トレーナーから、「なぜ、今話をしているのですか?」と問いかけられたのです。その時は「人が集まったら普通話すでしょう」と答えたのですが、僕は今起きていることを答えていただけなのですよ。それに対して、俯瞰しているような問いかけをされ続けているうちに、メタ認知が始まって、本質をすごく考えさせられたのです。「おれ、なんで話しているんだ?」って。僕らは「プロセス」によって動かされているということに気づいてしまい、それ以来コンテントはどうでもいいと思ってしまうくらいでした。そういう複層的な世界観があることを初めて知り、関心が高まって、文献を読んだり、いろんなトレーニングに参加しました。
いずれ仕事にしてみたいと思い、非構成の対話を重ねる、いわゆる対話型組織開発を自社でもやってみました。
———どんなことがおきました?(Tグループっぽく聞いてみる)
「うちの会社ってどう?」「今気になることある?」といった呼びかけで集まり、定期的に話し合う場を作りました。数回の対話を重ねたあるとき、一人のメンバーが発した「俺たちには思いやりがない」という一言に、全員が「それだ!」と納得したのです。対話を深めることで、私たちにとって意味がある言葉を紡ぐことができました。対話型組織開発でいう、エネルギーと説得力のあるイメージが出現したのです。「思いやりがない」から考えてみると、会社に来て「おはよう」と声をかけても、パソコンの画面を見たままで返事をする。一見お互いを尊重しているように見えて、実は関心を持っていない。そういった組織の課題が浮かび上がってきました。
———まさにコンテントじゃなくてプロセスに問題があったんですね。どのように解決していったんですか?
たった2つのことを決めました。まず、出社したら顔を見て挨拶をすること。もう一つは月に1回、カンパニーランチをすることです。シンプルで簡単な取り組みですが、普段のコミュニケーションの量と会社の雰囲気は確実に変わっていきました。この実体験から、対話型組織開発の可能性を実感することができました。
その後、僕自身が新しい領域に進みたい気持ちもあり、会社の未来について話し合う場も設けました。「今後、みんなどうしたい?」という呼びかけで対話を重ねていき、「残りたい人だけ残る」となりました。ある意味2回目の対話型組織開発の実践ですね。「会社を持続的にしない=会社を閉じる」というところまで対話型組織開発で落とし込みました。非常に合理的な理由で一人だけその会社に今でも残っていますが。
この「俺たち、解散!」って。それが2012年でした。組織の持続可能性のための組織開発でなく、組織を閉じるという組織開発の実践となりました。
———映画みたいですね。会社がいい感じにソフトランディングして。
学んだ技術と経験を活かすために、まずは「対話の学校」というファシリテーションの公開講座を始めました。その前に、笹塚にコワーキングスペース兼ワークショップスペースを作ったんです。「タイワハウス」って名付けて(笑)


———その後、企業研修なども手がけられたんですよね?
公開講座がきっかけになり企業にも呼ばれるようになりました。最初はリーダーシップ開発やファシリテーション研修を提供していました。ただ、対話の重要性が問われ始めた時期で、対話型組織開発のアプローチもどんどん取り入れていきました。
組織開発の場合は、「このワークショップをやってください」ではなくて、「うちの会社、なんか気になるんですけど...」みたいな漠然とした相談から始まります。僕はこれを「とりあえず(来て)案件」って呼んでいます(笑) とりあえずお伺いして、非構成の対話から始め、組織の本質的な課題を言語化して一緒に探っていくような。最初から見通しがつかない複雑な状況を、クライアントと共に探求する組織開発が好きなのです。具体的な施策は経営合宿や業部全体のワークショップが多かったです。

●社会人大学院進学の決意
———大学院進学につながるエピソードを教えてもらえますか?
10年ぐらい前から組織開発の世界に入って、食べていけるだけの技術はついていたし、この先も組織開発を続けていくだろうなと思っていました。でも自分の中にミッシングリンクがあって。一つは大学を卒業していなかったことです。それで2018年に通信制の産能大学に入学して2022年に卒業しました。もう一つは、「社会の役に立つようなことをしているのだろうか?」という問いです。これは大学院へ行って研究し社会に還元したいと思いました。また、残された30年というキャリアを見据えて、しっかりとした足腰を作りたいと思いました。それまでの実務は、クライアントのニーズに応えるためについつまみ食いのような学びになりがちでした。でも、本当の意味での専門性を身につけるには、体系的な学びが必要だと感じていました。いくつか候補がある中で、博士課程があること、自分の関心領域に近い組織開発と経験学習の研究ができることと、働きながら学べる環境が整っていることから立教大学(LDC)を選びました。
ただ......最初の受験では思わぬ壁にぶつかりました。
———ヤダ怖い、ドキドキする。なんですか?
2023年に初めて出願したのですが、大学卒業後1年以上経っていないという条件があったんです(笑) 僕は2022年の春に学部を卒業したばかりで、1年経っていませんでした。出願料まで振り込んでしまった後に大学事務局から連絡があって…. 受験できませんでした。返金いただき、その後出願条件も当時より緩和されたようですが。
———そんな落とし穴が!(笑)
はい(笑)でも、その期間を使って改めて「なぜ大学院に行きたいのか」を問い直すことができました。クライアントワークだけでは満足できない、もっと理論的な裏付けが欲しいし、もっと社会のお役に立ちたいという思いが明確になっていきましたね。
●学びと今後の展望
———大学院に進んでみてどうですか?
学びの関心領域が近いから、同じような価値観、視点を持つ人ばかりいると思っていたのです。しかし、そうでもないっていうか、多様性がありましたね。
普段の仕事は、案件毎にプロジェクトチームを組むのですが、一緒に仕事をしているメンバーはプロセスの言語化が得意ということもあって、自発的にコンディションを共有してくれます。他者がケアする必要やチームビルディングの必要性がほとんどないのです。一方、大学院はいろんな方がいらっしゃるので、しっかりチームビルドしたほうがいいということに気づかされ、チームリフレクションを隔週で実施することにしました。
それでも時にはチームメンバーとの関係づくりに課題を感じることもあります。僕の場合、相手を慮ることが苦手で、プロセスを明確に言語化して伝えたいし、伝えて欲しい程文脈的なタイプなのです。言語化することが苦にならないので、喋るアクセルを踏んでいるのが常態で、喋らないというブレーキでコミュニケーションをコントロールしているイメージです。だから周囲に対しても、「言えばいいじゃん」「言わなきゃわからないじゃん」という前提で関わってしまう。当たり前ですが、それ以外のコミュニケーションを求める方もいて、コミュニケーションの難しさに気付かされました。今まで居心地良い環境にいたので、その気づきは大きかったですね。
———吉田さんくらいキャリアの長い方でも、まだまだ人間関係の中に気づきのポイントがあるんですね。
1年の前期に、LWP(リーダーシップ・ウェルカム・プロジェクト)という実践的な学びの場があるのですが、チームメンバーと対話を重ねる中で、自分の癖や傾向に気づかされることが多くありました。例えば、私は目的志向なのでスピード重視でプロジェクトを進めがちですが、それによってメンバーの気持ちに配慮ができてなかったこともありました。しばらくしまっておいた事、自己課題に正面から向き合わせられる経験でした。
※LWP:人材開発・組織開発、リーダーシップ開発に必要な概念を課題解決を通して学ぶことを目的としたプロジェクト
———LDC2年目に向けての意気込みを聞かせてください。
卒論にあたるLFP(リーダーシップ・ファイナル・プロジェクト)は何に取り組むか、実はまだ迷っています。自分の研究テーマに寄せようとするとクライアントニーズが疎かになるような気がしますし、クライアントニーズに寄せると研究から遠ざかってしまうような気がして。むしろ、2本以上やってみようかなとも思っています(笑) というのも、これまでクライアント向けのレポートは書いてきましたが、学術の世界で通用するものはまったく書いたことがないのです。むしろ、クライアントニーズで1本練習で書いてみて、研究テーマでもう1本書く選択肢もあるかなぁと。
———2本ってこの人すごいこと言ってますよ。私は1本でも卒倒しました。心から応援しています!本日は貴重なお話をありがとうございました。