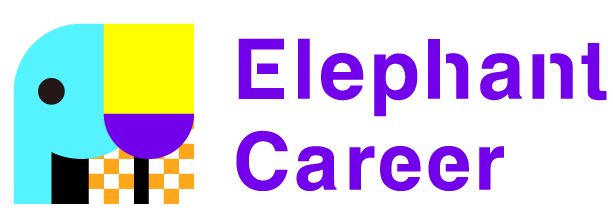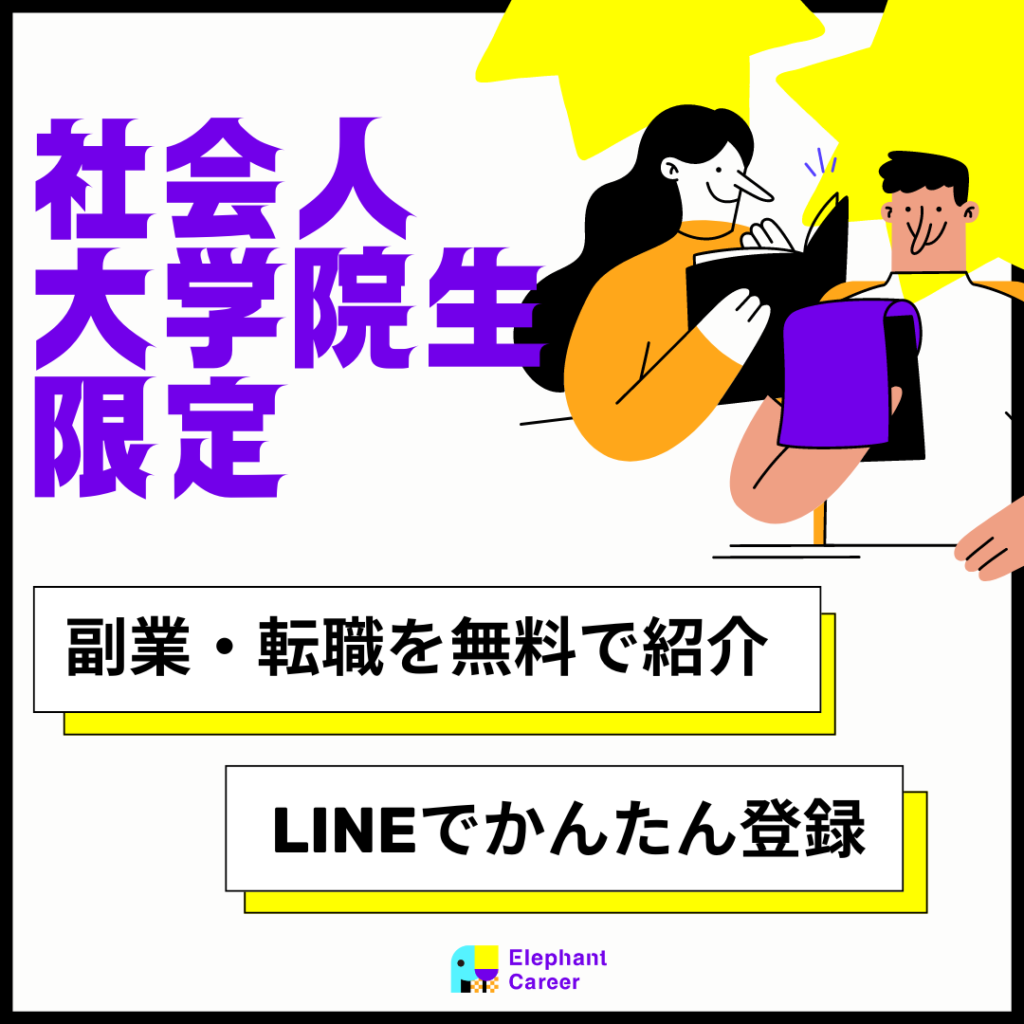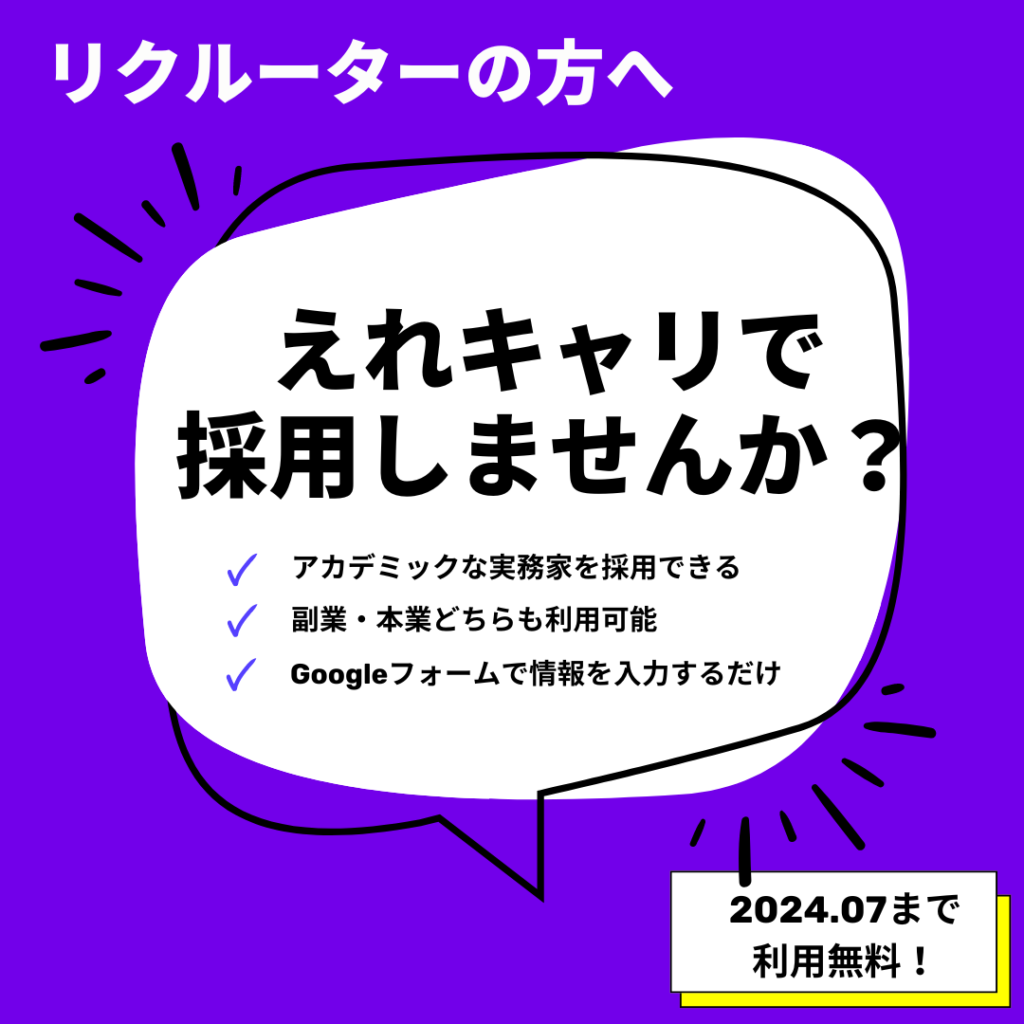社会人大学院の経験談を紹介する「先輩インタビュー」
今回は、University of South Australiaを修了された能間 寛子さんです。
社会人経験を経て大学院に進学し、現在は大学教員として活躍する能間 寛子さん。高校時代の留学経験から始まり、民間企業でのキャリア、そして研究者としての道を選ぶまでの経緯には、多くの人の背中を押すヒントが隠されています。今回は、その歩みを丁寧に紐解いていきます。
文京学院大学外国語学部准教授、同大学院外国語学研究科兼担准教授
専門:組織行動、異文化コミュニケーション
University of South Australia博士課程修了。Ph.D. (Business & Management)。九州国際大学国際関係学部助教、文京学院大学外国語学部助教を経て、現在同大学同学部准教授。同大学院外国語学研究科兼担准教授。現在は、大学及び大学院で組織行動関連科目及びコミュニケーション関連科目を担当している。
教員紹介:https://www.bgu.ac.jp/foreign/staff/hiroko-noma
文教学院大学院外国語学研究科:https://www.bgu.ac.jp/graduate-college/foreign
研究内容:職場における信頼関係の構築、職場のコミュニケーション(特に感情の役割や影響)
修了した大学院: University of South Australia博士課程
入学年月(年齢):2008年2月
修了年月(年齢):2012年4月
●原点は高校時代の"違和感"
——— まずは高校時代のお話から伺えますか?
福岡の出身で、地元の高校を卒業したあとは国公立大学に行くことが何よりもステータスである、という一つの価値観をみんなが共有してる環境で育ちました。でも私は、なぜそれだけが唯一無二の正しい選択だと言われるのかわからなくて、高校在学中に一年間オーストラリアに留学してみたんです。
———地方の高学歴高校あるあるですね、私も田舎出身なので、同じでした(笑)地元の国立・公立大学にいくことが、実は偏差値の高い首都圏の私大よりも上とみられる謎の文化。偏差値が高ければいいってもんでももちろん無いんですが...
そうそう、そうなんです......留学先で気づいたのは、自分の高校でこれが一番と言われていたことが、一歩外に出れば必ずしもそうではないということ。その気づきは、その後の人生の選択に大きな影響を与えることになりました。
それからもう一つ言うと、私はその当時「文化」とかそういうことを大学に入って勉強したいと思っていたのですが、高校の先生にそれを伝えても、あまりピンときてなくて。そんなの勉強じゃないくらいの勢いで否定されてしまったんです。
そして私がやりたいと思ってる「勉強」をなぜ人に止められなきゃいけないのかと。だからこそ海外に行っていろんなことを見てみたいと思っていたんですよ。
——— 小さな違和感を見逃さずに大切にされてたんですね。
●模索の時期 - 言語からコミュニケーションへ
———そこから、大学時代はどのような学びを?
最初は文化=語学かなとおもって、西南学院大学へ進んだんですが、大学で様々な教養科目を履修していく中で、コミュニケーション論という分野に出会ったんです。そこで気づいたのは、私が本当に学びたかったのは言語そのものではなく、人々の間のコミュニケーションや価値観・世界観だったということでした。
———その気づきが大学院進学につながったんですね
そうです。青山学院大学大学院の国際政治経済学研究科の国際コミュニケーション専攻に進学しました。大学院に通いながら、学生を対象にした短期留学や異文化交流プログラムを組んで海外に派遣するような仕事もしていました。
なんとなく修士を修了したら就職しなければならないと思い込んでいて、もっと研究したいという自分の心に従わずに修士修了後に就職をしました。でもやっぱり数ヶ月で、これは違うという違和感に襲われたんです。
——— またそのときも、違和感を大事にしてたんですね。
●社会人経験を経て再び学びの道へ
——— その時のお気持ちを覚えていますか?
頭が空っぽになるような感覚でした。もっと学びたい、インプットが足りないという思いが強くなって。そんな時、大学院時代の恩師に相談したら"じゃあ博士課程に行けばいい"とアドバイスをもらったんです。数年の準備を経て、博士課程に戻ることになるのですが、今度は日本の大学院ではなくオーストラリアの大学院にいきました。準備期間中に出会った方々に、自分の研究したいテーマについて相談していたら、オーストラリアをおすすめされたんです。
——— 研究テーマはどのように決まっていったんですか?
私の研究テーマは、オーストラリアにある日本企業における駐在員と現地社員の間の信頼関係の構築についてです。1990年代から経営学の分野で信頼研究が重視されるようになってきた中で、異文化間における信頼関係の促進要因や阻害要因、そしてそれぞれの文化圏における信頼を構築するプロセスの違いについて研究してきました。
——— 少しかいつまんで説明してくれますか?
異文化間で信頼を築くために最も重要なのは、信頼構築のためのサインの解釈が文化によって異なることに気づくということです。例えば、こちらが良かれと思って発したサインが、相手の文化圏では失礼や余計な行為として受け取られることがあります。また、職場で必要とされる信頼の種類自体が、文化によって異なる可能性があります。
——— 同じハンドサインでも、ある地域では友情の証であるものが、ところ変われば屈辱的なサインだった、みたいな話はよく聞きますよね。
——— 文化による信頼の違い、克服するにはどうすれば?
まず自分が期待する信頼とは何かを理解し、同時に相手が求めている信頼も理解する必要があります。ただし、信頼について考えるのは、多くの場合それが失われかけている時です。平常時にはあまり意識されないため、信頼の危機が訪れた時には既にバイアスがかかっていることも多いのです。

●博士課程での挑戦
——— 博士課程では経済的な面で苦労されませんでしたか?
実はラッキーなことに、奨学金を得ることができました。授業料は全額免除で、さらに生活費として十分な額の奨学金をいただけました。週8時間までアルバイトが許可されていて、その範囲内で大学の非常勤講師やTA、RAの仕事もさせていただきました。博士課程は元々人数が多くないので競争率から言うと修士課程の奨学金よりも競争率が低いと思います。
それから国際化を促進している大学や大学院の場合、留学生に対して授業料免除や生活補助、渡航費が出ることもあります。
——— 研究生活での苦労はありましたか?
最初の数ヶ月は本当に大変でした。3-4年の研究のブランクがあったので、研究マインドセットを取り戻すのに時間がかかりました。単に本を読むことと研究することは全く異なります。でも、指導教授や同じ研究室の仲間に恵まれて、少しずつ研究者としての視点を養うことができました。
研究に必要な知識を英語でインプット・アウトプットしていたので、その後日本に戻った時にはそのまま英単語を使っていいのか、日本語に代替した方がいいのかも苦労しましたね。
——— 博士号取得後はどのように?
博士課程の後半から、現地の大学で学部と大学院のコースをいくつか担当させていただいていました。自然と"このまま研究・教育の道に進みたい"という思いが強くなっていきました。でも、どの国で教員としてのキャリアを始めるべきか、すぐには決められなかったんです。
とりあえず日本の大学にも応募してみようと思って。すると運良く、4月からのポジションをオファーいただけました。最初は九州国際大学でしたね。地元の福岡だったので、スタート地点としては理想的でした。
——— その後東京に移られたそうですが。
そうですね。2年ほど九州で教鞭を執った後、より広い活動の場を求めて東京に移ることを決めました。当時はオンライン環境が今ほど整っていなくて、国際学会や研究者との交流のほとんどが東京を中心に行われていました。研究活動を深めていくには、東京の方が適していると判断しました。

●研究者としての気づき
———実務経験を経てアカデミックな研究分野に戻るというキャリアパスについて、お考えをお聞かせください。
実務での経験を"証明したい"という気持ちが強くなりすぎると、それは自分のための研究になってしまう。でも本来は、その経験と学術的な知見を組み合わせることで、社会にどう貢献できるかを考えられるといいですね。
論文を書く際にも、自分の経験や考えに固執せず、新規性、独自性、社会貢献性を重視する必要があります。長い間自分が信じていた考え方や価値観とは異なる考え方、価値観、主張の研究者はたくさんいます。実務経験が長くなると、受け入れがたいこともあるかもしれません。単に自分の経験を語るだけでは不十分で、これまでの学術的知見と実務経験をバランスよく組み合わせることが重要です。
———私も大学院で論文を書く時の基本として教えられました。確かに独りよがりになってはいけませんよね。
●社会人の学び直しを考える人へ
———社会人大学院への進学を迷っている人が多いと思います。どんなアドバイスをされますか?
本来大学院での学びは、"最短距離で資格を取りたい"とか"即戦力になれる学びを"という単なるスキルアップの場ではないと思っています。考える力を身につけること。それは遠回りに見えて、実は自分の可能性を最大限に広げることになりますし、もっとオープンな気持ちで面白そう!って思えることを進学する原動力にして欲しいですね。
確かに社会人は時間やお金の制約があり、家族への配慮も必要です。しかし、自分の興味に従って学ぶことで、必ず今までのキャリアや学びとどこかでつながってくると思います。最短距離で目標に到達することも素晴らしいですが、探索的に学ぶ方が、自分なりの道を見つけたり、思いつかなかったようなキャリアに出会ったり、長期的には充実した人生につながるのではないでしょうか。
———なるほど、ポジティブな捉え方ですね。

———教育者としての立場からは?
近年、目的ありきの学びが重視されすぎていることを懸念しています。具体的なゴールへの直接的なつながりが見えにくい学びは無駄だと思われているような感じがすることがあります。 "何になりたいからこの学部を選ぶ"という直線的な考え方が悪いわけではありませんが、可能性を狭めてしまう危険があります。大学教育の本質は、スキルの習得だけでなく、考える力を身につけることです。4年後、5年後に、現在ある職業が消えているかもしれない時代において、回り道を恐れず、興味に従って学ぶ姿勢が重要だと考えています。
学生たちには、"これが正解"という一つの道だけでなく、様々な可能性を探索してほしいと思っています。目標を立てて最短距離で達成する、という観点から見れば、私は回り道に見える選択をしてきたと思いますが、結果として今の自分を作ってくれました。人生100年時代、キャリアは必ずしも一直線である必要はない。むしろ、様々な経験を重ねることで、独自の視点や価値を生み出せるのではないでしょうか。
そのためにはまず自分が学びたいと思っていることを自分のことばで言ってみる。そしてそれをアカデミックな環境にいる(いた)人がアカデミックな言語で言うと、こうなるよっていうのを伝えてあげる機会があると、まずはこの分野のこれを勉強すればいいんだっていうのがわかると思うんです。私にはそういう大人が周りにいたら良かったなと思っています。
———そういう壁打ち相手がいたら世界が広がりますよね!本日は貴重なお話をありがとうございました。