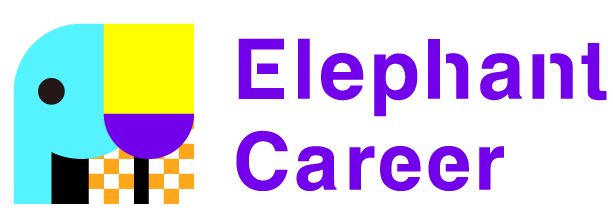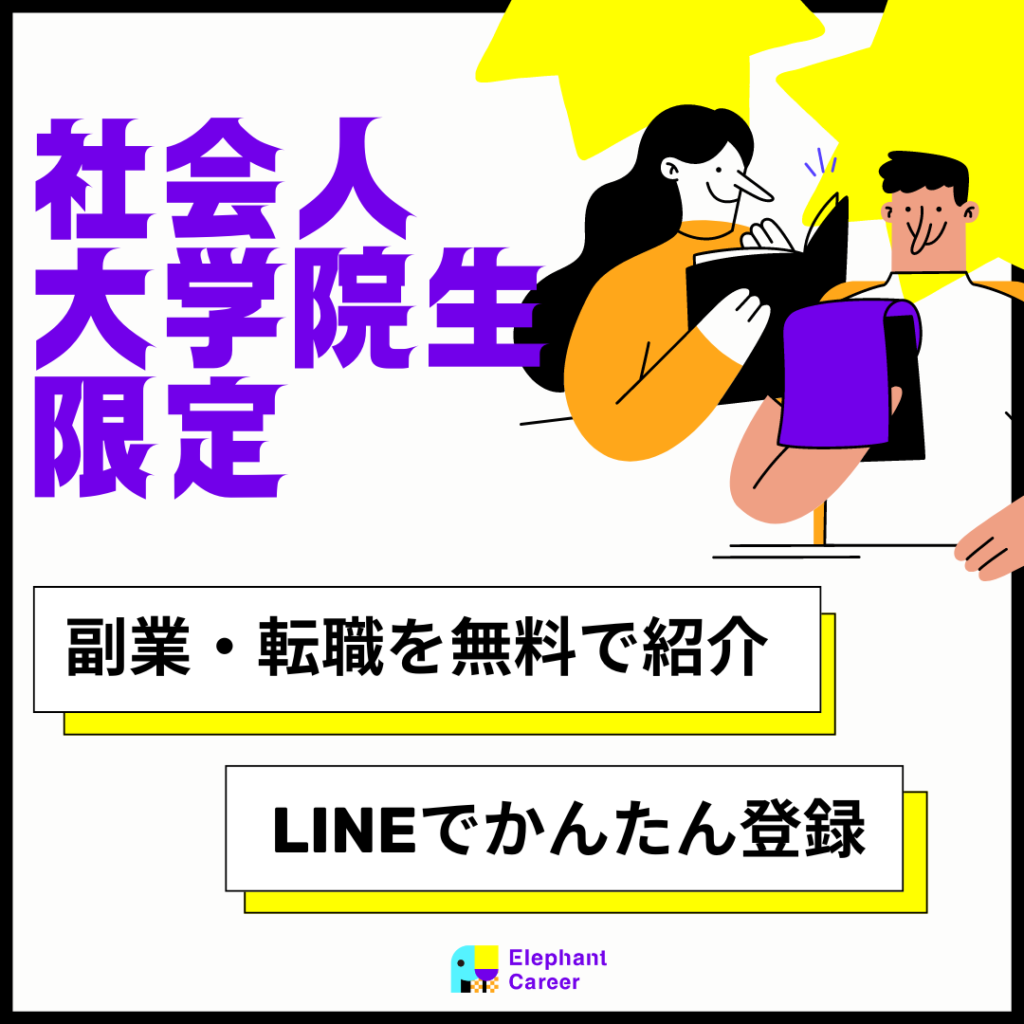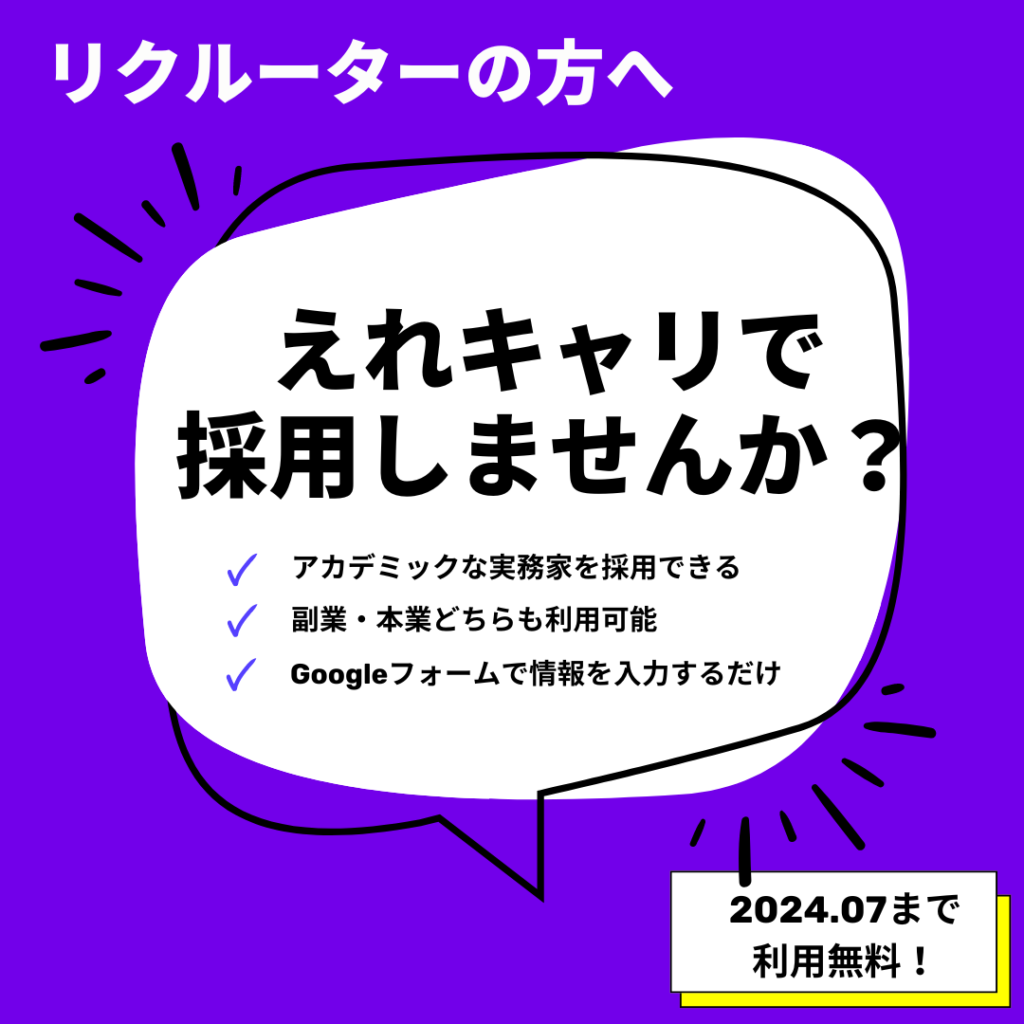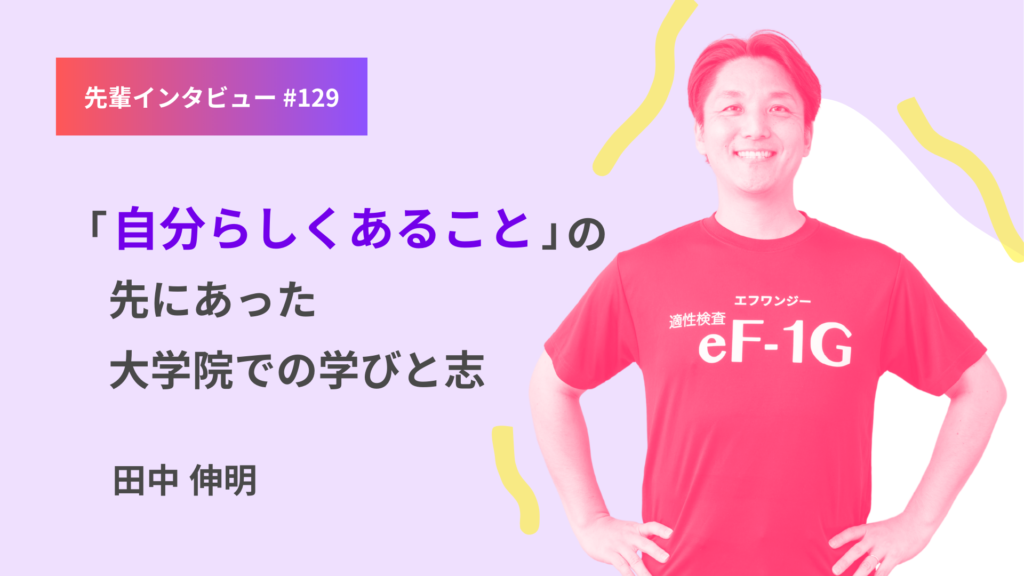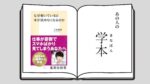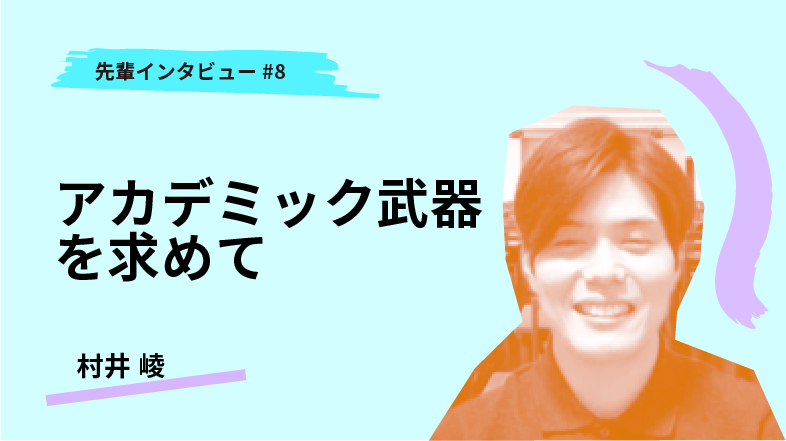
働きながら学ぶ人を紹介する「先輩インタビュー」
今回は、パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社で事業部人事をご担当の村井さんにお話を聞きました。
1996年生まれ、愛知県出身。小学校三年生から大学四年まで硬式野球部に所属。立命館大学では、スポーツマネジメントを学ぶ。2019年よりパナソニック オートモーティブシステムズ株式会社で営業部門の事業部人事を担当。2021年に立教大学院リーダーシップ開発コースに進学し、2023年に修了予定。
●ぶん投げサーベイフィードバックでの痛い経験
———— 立教大学院リーダーシップ開発コース(LDC)のグループインタビューでご一緒して以来ですね。今日はよろしくお願いします! 早速ですが、村井さんの経歴を教えてください。
2019年にパナソニックに新卒で入社し、入社時から営業部門の事業部人事を担当しています。今年で4年目になります。人事部では、人材開発・組織開発を広く担当しています。
学部時代に組織コミットメントについての卒論を書いたので、人や組織への興味はありました。当時野球部に所属していて、上下関係や体育会系な慣習に疑問を覚えて、そういった文化・慣習が組織にどのような影響を及ぼすのかを調査し、卒論を書きました。院生に重回帰分析のやり方などを習って、なんとか卒業しました笑
————では、学部時代のテーマをより深く研究しようと思ってLDCに?
いえ。どちらかというと、人事という仕事で全く役に立っている実感がなくて、アカデミックな武器が欲しいと感じて進学しました。実は、一つ鮮明に覚えている仕事がありまして。入社一年目に、組織サーベイの結果を現場にフィードバックすることになったのですが、当時はサーベイ結果を現場に共有し、アクションプランの検討は現場でよろしくね、というスタンスでした。結果はまとめたものの、どう解釈し、何が問題なのかを特定するというプロセスは現場に丸投げ。自分自身、現場のこともわからないし、問題を見立てる勘所もなくて。丸投げした現場からは、明らかに信頼されてない空気が伝わってくるし、人事として価値を出せてないもどかしさで一杯でした。
———— それは悔しい場面ですね。人事としても社会人としても肌感がない中で、現場に示唆のある情報を提供するって難しいですよね。
そうですね。上司や先輩は長い経験の中で培った知識や勘所をもとに現場と会話していて、そこはすごく尊敬します。ただ僕は、それにアカデミックな拠り所をプラスして現場と対話できるようになりたいと考える派でした。
———— すごく共感します。私も村井さんと同じ境遇で、新卒で入社した会社で人事としてのキャリアをスタートしました。「この会社での正=世の中一般的な正なのかどうか」自信が持てず、視野を広げるためにアカデミックに人事を学びたいと思ったのが進学のきっかけでした。
経験が浅い、視野が狭い分、不安になりますよね。学びたいな〜と色々と調べている中で、LDC主査の中原先生のブログを見つけて、この人の元で学びたい!と思い、進学を決意しました。これ!と思ったら他を比較検討するタイプではないので、LDC以外は考えませんでしたね。
●人事としても社会人としてもレベルアップできる場
———— 今は大学院2年目だと思いますが、期待通りのアカデミックな知見は得られそうですか?
おかげさまで、アカデミックな知識を増やすことで、仕事に対する「視点」が増えたなと感じます。例えば「早期離職が目立つ」という現場課題に対して、理論を用いてアプローチし、解決のプロセスを導き出すことが徐々にできるようになっていると感じます。今までは自分の勘と経験という視点しかなかったけど、アカデミックな視点や、グループワークなどで同期と意見交換して得た視点が自分の中に取り込まれてきている感覚です。
入学して、なんとなく授業を受けてるだけではダメってことに早い内に気付けてよかったなと思います。
———— なるほど、授業だけではダメという部分を具体的に教えて欲しいです。
僕が大学院にきたのは、研究者になりたいからではなく、あくまでも人事としての実務家スキルを上げるためです。入学前は、大学院に入学して良い成績さえ取れれば、そのスキルは勝手に上がっていくものと思っていました。
でも実際は、授業やグループワークで学んだことをいかに実践に転用できるかが重要でした。授業を受けるだけで満足、学んだ気になってはダメで、学びを実践に活かし現場・経営にお役立ちできるレベルまで昇華するのが私の仕事だと改めて考えるようになりました。どんなお役立ちができているか?そのお役立ちによって何か変化したか?常に自問自答しています。
———— 大きなマインドチェンジですね。具体的に仕事の進め方などで変わった点はありますか?
そもそもの話になっちゃいますが、「仕事の仕方」を学べたなと思います。LDCではグループワークが多くあり、研修を作ったりワークショップを企画します。このプロセスは仕事とよく似ていて、企画→実践→振り返りのサイクルが必ず発生します。仕事だけでは数年かかってしまう試行回数を大学院という場でもこなすことができるので、一年で数年分の仕事をこなしている感覚です。舞台に立つ回数が増えて、自信がつきました。教授はもちろんですが、同期にも師と呼べる人がたくさんいて、常に刺激をもらっています。
●在校生にSNSでコンタクト
———— 受験準備はどのようにされましたか?
LDCの公式インタビューに答えていた在校生の方にfacebookでコンタクトして、相談に乗ってもらいました。8/16にはじめて在校生の方に話をきいて、そこから受験準備をして、入学試験は年明けだったので約5ヶ月くらいの準備期間でした。その他にもTwitterやfacebookで在校生らしき人を見つけたらフォローして、内情を探ってましたね笑
———— 参考にした書籍等はありますか?
経営学に関しては、入山先生の世界標準の経営学を読みました。経営学ではもはや必読書ですね。特にLDCは「人と組織について学ぶ」とはいえ、事業に資する人事を育てることがモットーなので、必要最低限の経営学知識が求められます。入学準備だけではなく、入学後の授業でも役に立ちました。分厚いので、辞書的に使うのがおすすめです。その他人事系であれは、以下を受験準備として読みました。
-
中原淳・中村和彦『組織開発の探究』ダイヤモンド社、2018年
-
中原淳『経営学習論ー人材育成を科学する』東京大学出版会、2012年
-
中原淳他『企業内人材育成入門』ダイヤモンド社、2014年
-
中村和彦『組織開発 活き活きと働ける職場をつくる』. 光文社新書、2015年
-
舘野 泰一・高橋俊之(編)、中原淳(監修)『リーダーシップ教育のフロンティア』、2018年
-
鈴木竜太・服部泰宏『組織行動』有斐閣ストゥディア、2019年
-
三谷宏治『新しい経営学』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2019年
-
スティーブンP・ロビンス『組織行動のマネジメント』ダイヤモンド、2009年
-
鈴木竜太・服部泰宏『組織行動』有斐閣ストゥディア、2019年
———— これは大学院関係なく、人事の人にとっては最高のリストですね。ありがとうございます! 研究計画書はどのように準備されましたか?
立命館時代の教授にフィードバックもらいながら、整えていきました。計画書は「熟達*」について書きました。
熟達*とは
認知心理学や認知科学においては、ある領域の専門的なトレーニングや実践的な経験を積み、特別な技能や知識を獲得した人を「熟達者」と呼ぶ。(『経験からの学習』松尾睦/著)
———— 教授に添削してもらえる環境は羨ましいです!余談ですが、大学院の在学生や卒業生は、もともとの顔見知りでなくとも相談されれば添削や相談に乗ってくれる人も多いと聞きます。えれキャリを読んでる人はぜひ気軽にSNSでコンタクトしてみて欲しいですね。
あと一点受験準備で村井さんにぜひ聞いておきたかったのが、お金の話です。私も村井さんも社会人3年目で進学してますが、進学費用の問題はどうクリアしましたか?私は当時、貯金が足りなくて夫に借金して進学しました。2年間の間になんとか返済できましたが...。
お金は、僕も全然足りないですね!でも、両親から借りたりとかはなく、ボーナス全突っ込みと貯金からなんとかやってます。
———— 立教はまだ教育訓練給付制度の対象じゃないので、きついですよね....。岸田さんがリスキリングに4000億投資すると言ってましたが、今後どうなるか期待ですね。
●いつかは社会人を教える側に
———— 卒業後のビジョンなどはありますか?
まだ卒業もしてないのにって感じですが、いつかは実務家教員として教える側に回りたいですね...。大学院の授業を受けていて、実務で活かすにはラストワンマイル足りないなって思う場面が多くて。
例えば、一年目夏の組織行動論の授業がすごく面白くて、期待理論や道具理論について学んだのですが、日々実務の課題に向き合っている人がこれらの理論を知ったところで目の前の課題を解決するプロセスとして使うにはちょっと遠いなと感じたんです。
———— 実務と理論の橋渡しですね。社会人を受け入れることができる大学院の上限がある中で、実務家が教える側に回っていくのはエコシステムとして優れていますし、キャリアの選択肢としても広めていきたいですよね。
そうですよね。LINEの青田さんなんかは、理論を取り入れつつも実務で自分が培った言葉でそれを解釈して現場で使える知識として取り込んでいて、すごいなって感じます。青田さんが解説している理論のスライドは、現場の人にとっても馴染みがあるし、スッと入ってくる。僕もそんな橋渡し的な人になりたいなと思っています。
———— いいですね!まさにLDCが謳う「アカデミックプラクティショナー*」ですね。最後に、どんな人にどんな人に社会人大学院を勧めますか?
行きたいと思ったら、みんないくべきです!入学当初は「まだ若手だし可愛がってもらえないかな〜」なんて邪な気持ちを持ち合わせていましたが、良い意味で裏切られました笑。もちろん同期はみんな親切だし、力になってくれますが、年齢や経験関係なしに対等に接してくれます。
アカデミックプラクティショナー*とは、アカデミックの理論や知識を用いつつ、現場と対話しながら自ら実践し続ける人のこと
———— 学部と違って、浪人なんて概念もないですし、本当にみんな対等ですよね。もちろんお互いの経験や価値観にリスペクトしつつですが。社会人大学院は、立場や年齢から自然と生まれる上下関係なんかも存在せずフラットに議論できる稀有な場ですよね。村井さん、今日はありがとうございました!
授業
- 1年時:金曜18-22時半(毎週)、土曜9-17時(毎週)
- 2年時:金曜18-22時半(毎週)、土曜9-17時(月1,2回程度)
グループワーク
- 1年時:週2-3日21-23時
- 2年時:ほぼなし