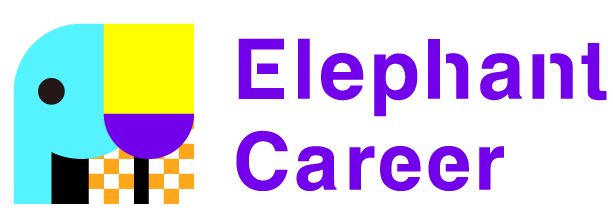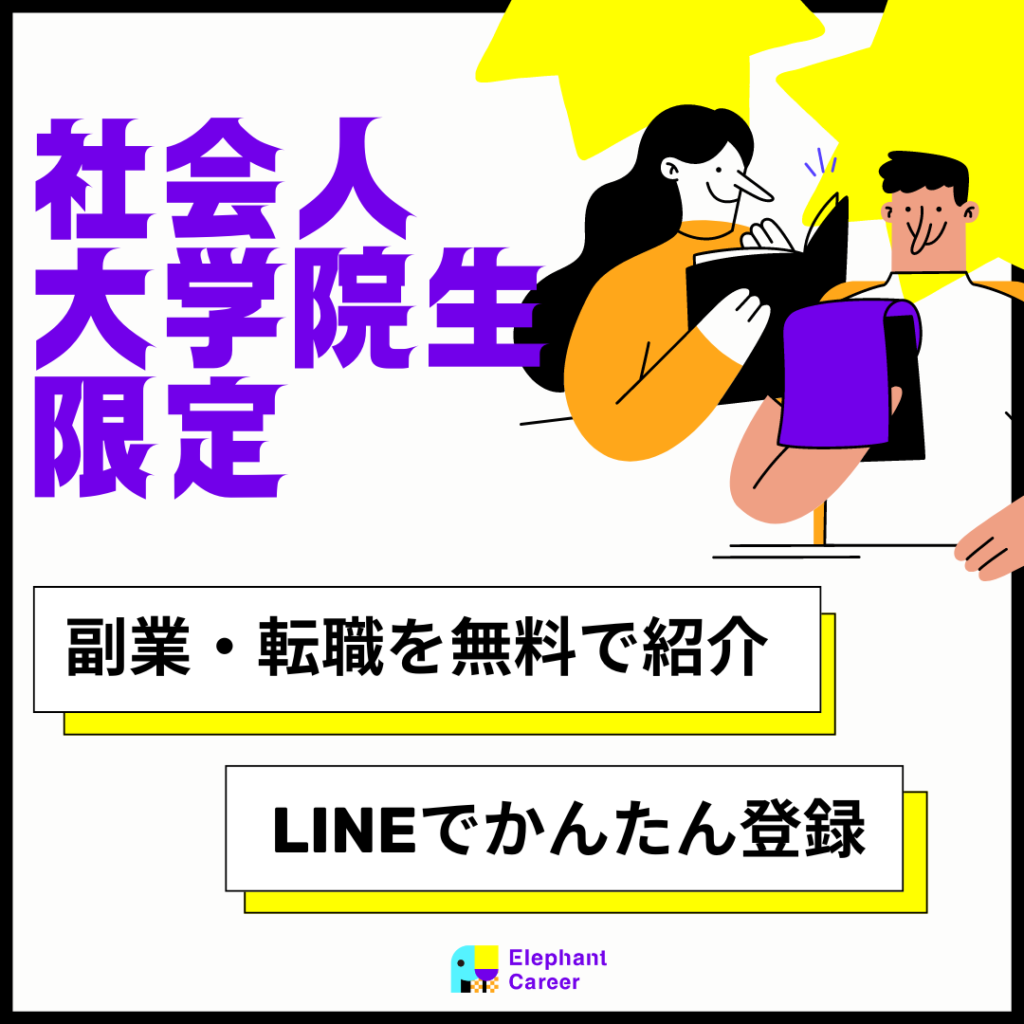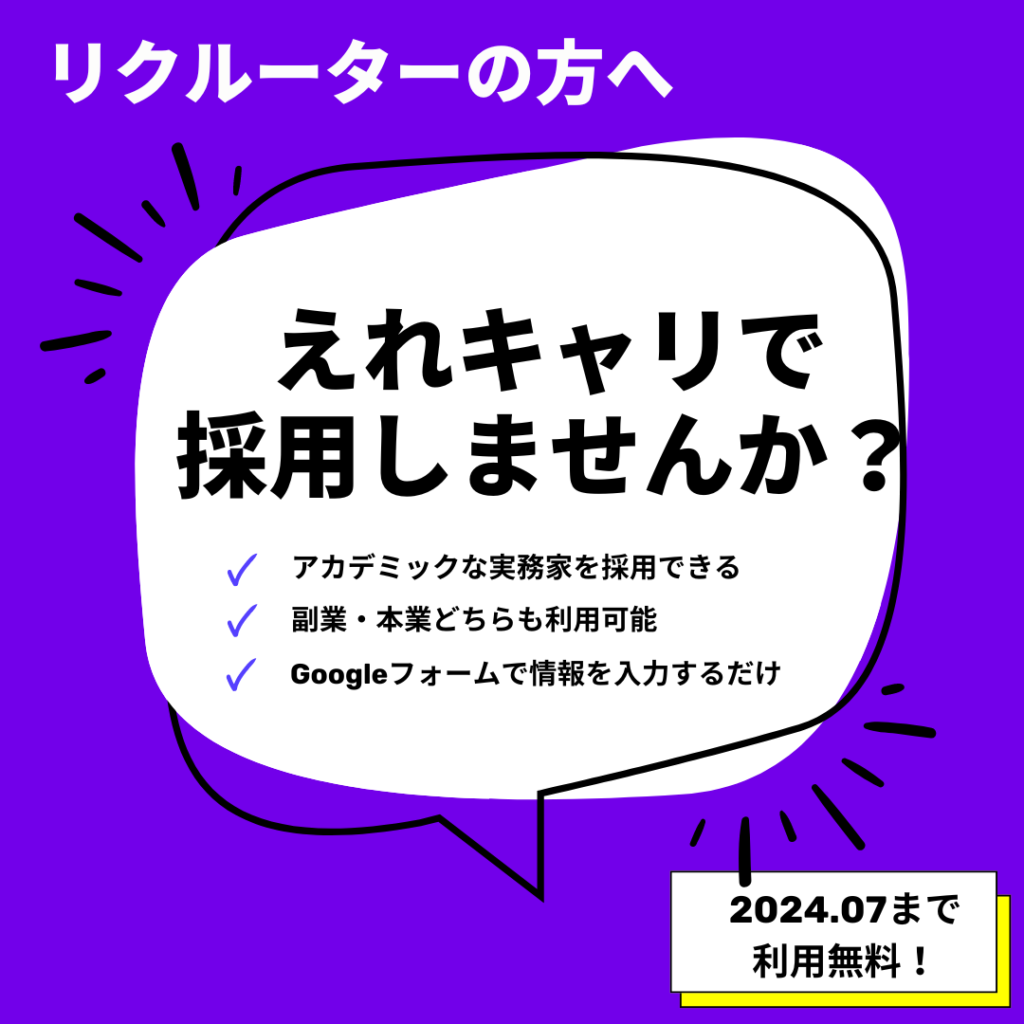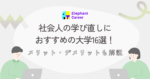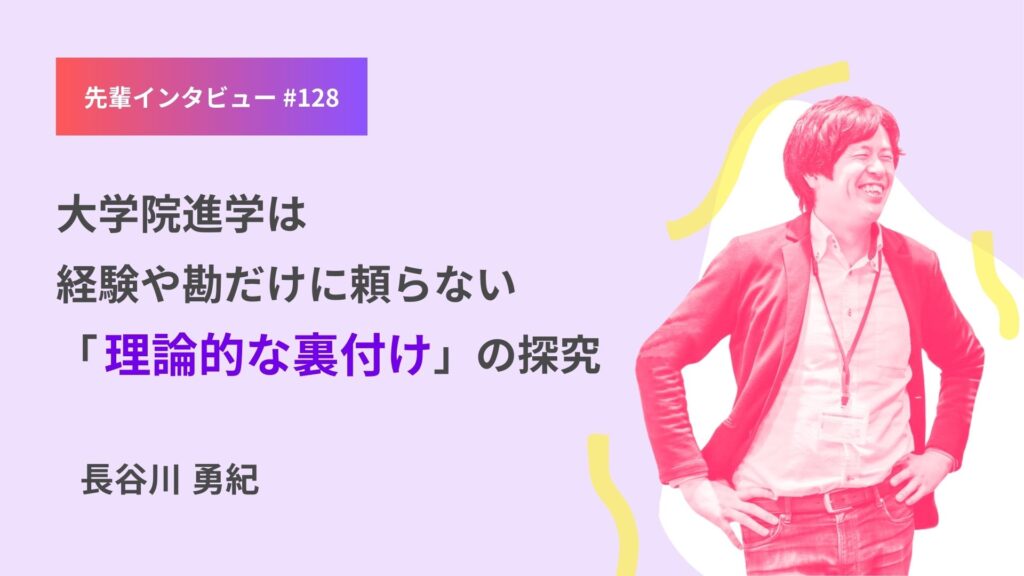
社会人大学院の経験談を紹介する「先輩インタビュー」
今回は、立教大学大学院経営学研究科経営学専攻リーダーシップ開発コース(LDC)在学中の長谷川 勇紀さんです。
教育とビジネスの領域を行き来しながら、独自の視点を築く長谷川さん。現在、社会人大学院で学びながら、組織開発や人材育成の最前線で活躍されています。今回は、キャリアの大きな転換点となった社会人大学院への進学について、その背景にある豊富な経験や思いを詳しく伺いました。
東京学芸大学卒業後、株式会社セルムにて民間企業向け人材開発・組織開発業務に従事。2014年、NPO法人カタリバに入職。福島県立ふたば未来学園高校の学校支援コーディネーターチームを立ち上げ、学校の中の放課後の居場所「双葉みらいラボ」を開所。2018年から、福島県復興教育アドバイザーとして、福島県全体の探究的な学びの充実に向けた戦略づくりを担う。2021年、島根県松江市に移住し、現在は島根県教育委員会に所属しながら、全県の高校魅力化に取り組む。一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームディレクター。認定NPO法人カタリバパートナー。キャリアを積む中で気づいたことを大学院で学ぶことで学術的なアプローチを実務に活かしたいと、2023年4月立教大学大学院経営学研究科経営管理コース(LDC)入学
カタリバ~ふたば未来学園高校支援〜https://www.katariba.or.jp/activity/project/futaba_school
地域・教育魅力化プラットフォームhttps://c-platform.or.jp/
研究内容:都道府県教育委員会事務局における高等学校支援指導主事のワーク・エンゲイジメント向上に関する研究
在学中の大学・大学院: 立教大学大学院経営学研究科経営学専攻リーダーシップ開発コース(LDC)
入学年月(年齢):2023年4月
修了年月(年齢):2025年3月
●消極的な自分が選び取ったもの
——— まずは長谷川さんの経歴からお聞かせください。
はい。私は新潟の出身なんですが、高校を卒業して東京の大学に進学しました。教育学部を選んだのですが、実は最初から教員になることを強く志望していたわけではなくて(笑)
比較的、消極的な選択だったと思います。ただ、いろんな学部を見ていく中で、教育という分野は他の分野と比べると関心が持てそうだと感じたんです。それに、18年間ずっと新潟にいた自分にとって、東京に出てみたいという気持ちも大きかったですね。
———大学時代はどのような学生生活を送られていたんですか?
お恥ずかしながら、入学当初は特に目標もなく、なんとなく過ごしていました。高校時代は陸上部だったので、大学でも何となく陸上部に入部したんですが、「このままでいいのかな」という思いが徐々に強くなっていきました。
転機になったのは、大学の課外活動でした。ふと目にとまった大学生協の掲示板で、子どもたちと直接関わるボランティア活動に参加できる機会を見つけて。それが私にとって初めて「主体的に選んだ学び」だったんです。
●「人を導く」を目の当たりにした瞬間
———ボランティアとは具体的にはどのような活動だったのでしょうか?
最初はキャンプリーダーとして活動を始めました。夏休みに子どもたちを連れて野外活動をしたり、土日に川遊びをしたり。今でいうプロジェクトアドベンチャー的な活動です。
特に印象に残っているのは、2,30人ほどの子どもたちを担当した経験です。そこでは単に遊ぶだけでなくて、野外教育という観点からしっかりと目標設定をして、活動後の振り返りまで行ってました。子どもたちの主体性や協調性を育むことを意識していましたね。

———なるほど〜。立教の学部のBLP(ビジネスリーダーシッププログラム)みたいな。構造としては似てますよね。その頃から活動を通して学んでいくっていうのが長谷川さんの現在の働きのルーツになっていそうですね。
たしかに知識をインプットするというよりも実践を通じて、それをリフレクションして学んでいくっていうところはなんかその当時から子供たちを通して実感値をめちゃくちゃ得ていましたね。
———その経験を通して芽生えたこととかキャリアに影響したことって何かあります?
そうですねー、あるキャンプリーダーの先輩の姿を鮮明に覚えてますね。その方は、テント片付けという一見単純な作業を、子どもたちが楽しく取り組める活動に変えてしまったんですよ。「よし、片付けるぞ!」という掛け声とともに、アーチを作りながら片付けていく。その様子を見て、「人を導く」ということの面白さに気づきました。
――お片付けの中から!長谷川さんのアンテナの立て方がすごいですね!
●先輩との出会いと世界一周が教えてくれたこと
———その後、休学して世界一周の旅に出られたそうですね。
はい。きっかけは大学の先輩との出会いでした。その先輩が1年間大学を休学して世界中を放浪し、帰国後に自費出版で本を出版。その印税でアフガニスタンに学校を建てるというプロジェクトを始めたんです。
その姿に強く刺激を受けて、私も1年間休学することを決意しました。特に印象に残っているのは、世界中を周っている途中で入学したデンマークのフォルケホイスコーレでの経験です。そこで「学びとは生涯をかけて育んでいくものだ」ということを強く実感しました。
※注)フォルケホイスコーレとは、北欧独自の教育機関。試験や成績が一切ないこと、民主主義的思考を育てる場であること、知の欲求を満たす場であることが特徴。
———フォルケホイスコーレいいな〜!帰国後はどのような活動を??
大学に戻ってからは、その経験を活かして、教育に関する活動を再開させていきました。それがNPO法人カタリバという団体との出会いにつながります。当時のカタリバは、高校生と大学生が車座になって対話する活動を中心に行っていて、何百人、何千人の高校生たちと話す機会を積み重ねていきました。
高校生に自分の経験を語るなかで、「体験を通じた学び」の価値を再確認できましたし、教育に対する私の考え方も大きく変わっていきましたね。
●悔しい経験をバネに
———大学卒業後は、どのようなキャリアを選択されたんですか?
教育への関心は強かったものの、ダイレクトに学校の教員という道は選びませんでした。塾とかいわゆる知識学習もなんか違うと思っていて。学ぶ、成長する、変化に対する関心はめっちゃあって、面白みを感じていたことは覚えています。
教育学部にいたので幼稚園・小学校・中学校・高校の教員免許を取得し俯瞰することができたんですけど、じゃあその子たちが出た社会はどうなっているのかっていうところを、もっと自分の中で見てみたいなっていう気持ちも出てきて。
———面白いですね。広いですね。
なんというか、対象とかあんまりこだわってないっていうのもあったんでしょうね。自分の中でその学ぶということとか、成長するとか、そういった人の変化みたいなものに対する関心は強くあったんですけど、それが子供であろうが大人であろうがなんかその瞬間に立ち会えることに面白みを感じたっていう部分が強かったのかな?って。
それで社会人教育の領域をちょっと色々見ていた時に成長や変化のためのトリガーをつくっていくことの方がいいのかなと思って、外部との接点を持ちながら教育に関わる道を模索する中で、人材育成の分野に興味を持ちました。そして、既製のコンテンツを提供するのではなく、クライアントの課題に対してカスタマイズした解決策を提案するというアプローチの会社に7年ほど勤務しました。
———その間、大きな転機が訪れたそうですね。
はい。4年目から5年目にかけて担当した大型案件で、大きな失注を経験したんです。提案内容自体は良かったのですが、実際の研修運営に対する不安から、クライアントの信頼を得られませんでした。この経験から、「力をつけなければ何も価値を生み出せない」ということを痛感し、単純ですが、マネージャーになることを目標に据えました。
その後2年ほどで当時の最年少マネージャーになることができ、ようやく仕事の面白さを実感できるようになりました
———そこから教育の現場に戻られたわけですね。
はい。カタリバに転職することとなり、特に印象深かったのが福島県での学校づくりのプロジェクトです。震災後の双葉郡で、5つの休校になった高校の思いを引き継ぐ形で新しい学校を作るという、国家プロジェクトに近い取り組みでした。避難先を転々とした生徒たちの中には、中学校で力を発揮し切れなかった子も多くいました。その子たちの良さを伸ばしながら、地域の未来を担うリーダーを育成するという、非常にチャレンジングな取り組みでした。

●勘と経験だけじゃないアプローチ
———教育の現場での経験が、社会人大学院進学のきっかけになったんですか?
子どもたちの学びを支えるには、教職員も含めた組織全体が生き生きと活動できる環境が必要だと。経営塾で半年間のプログラムを学んだり、システムコーチングなども学びましたが、どこか物足りなさを感じたり、やはり断片的な学びになってしまうと感じました。
第一線で働く教育者たちと接する中で、「理論的な裏付け」の重要性を強く感じるようにもなりました。経験や勘だけでなく、学術的な知見に基づいたアプローチが必要だと感じたんです。
また、組織づくりの専門家として、教育委員会の中で新しい取り組みを始める中で、より深い専門知識の必要性も感じていました。
———兵庫教育大の教育政策リーダーの養成コースも考えていたとか。なぜLDCに?
いまはむしろ、そちらの大学院にも次のステップとして通いたいという思いも強くありますが(笑)、その当時、LDCに惹かれて選んだ理由は大きく2つありました。
1つ目は、組織開発に特化したプログラムだということ。私自身、教育現場で組織変革に携わってきた経験があり、その経験を理論的に深められる場所を探していました。
2つ目は、実務家教員による実践的な学びが得られると感じたからです。理論だけでなく、現場での応用を常に意識したカリキュラムに魅力を感じました。
———実際の大学院生活について、もう少し具体的に教えていただけますか?
はい。私のゼミでは、教育委員会における指導主事のワークエンゲージメントについて研究しています。面白いのは、理論を学ぶだけでなく、実際の現場で検証できる機会が多いことですね。
例えば、ジョブクラフティングという概念を使って、現職の指導主事の方々の働き方改革に取り組んでいます。理論を学び、それを実践で試し、その結果をまた研究に活かすという循環ができています。
———どのような介入をされたんですか?
教員時代から指導主事になるまでの経験を、キャリアストーリーとして語っていただくところから始めました。そこから自分のライフテーマを抽出し、現在の仕事をジョブクラフティングする、という流れです。4名の指導主事の方々に協力いただき、質的研究として進めています。
———なるほど〜。ナラティブをちゃんとストーリーとしてつなげてもらうってことですね。
質的研究って若干自由演舞的なところがあるからいいのかなと思いつつも。ジョブクラフティングを皆さんにやってもらって、ワークエンゲージメントも活力とか熱意とかが高まっている様子は確認できたかなっていうふうには思ってます。
実際その様子を見て一番価値あったのは、そういう働きかけって教育委員会の中であんまり全然なかったので、そういう指導主事に向けたその学びの機会を作るということを、ちゃんとその担当を置いて次年度以降進めるのがいいんじゃないか?っていうような話にはなってきたことですかね。人事、人材育成機能を作るっていうところに今持っていこうとしてますね。
———めちゃめちゃでかい変化じゃないですか、それって!
できればね。そこのポジションに僕が関わり続けさせてもらって、今回の 4 人を一つのサンプルケースにして他部署とかにも展開していきつつ、そういったことを同じような課題感のある他県の教育委員会内でも人材開発、組織開発の重要性とか、そういうメッセージを発信していけるといいなって思ってます。
それが、今回の研究に全面的に協力してくれた島根県教育委員会への一番の恩返しになるかなと思って。
———LDCの進学で当初の想定と異なった点はありますか?
チーム学習の多さには驚きました。個人での学究的な学びをイメージしていたのですが、実際には異業種の仲間とプロジェクトを進める機会が多くありました。その中で、自分のリーダーシップのあり方について深く考えさせられました。
———(笑)
チームのパフォーマンスを高めるために、自分がどのような影響力を発揮できるのか、2年間かけて考え続けました。リーダーシップ開発が、LDCのプログラムの中核にあることに、今更ながら気づかされた感じです(笑) 「自分が変わらなければ組織は変わらない」という言葉の意味を、身をもって実感しました。

———仕事と研究の両立で苦労されることはないですか?
......(笑) 正直、かなり大変です。平日は仕事で忙しく、週末は研究や課題に追われる日々です。でも、面白いことに、仕事と研究が相互に良い影響を与え合っているんです。
仕事で直面する課題が研究のヒントになったり、逆に研究で学んだ理論を実務に活かせたり。そういう相乗効果を実感できるのが、社会人大学院の醍醐味だと思います。
———次の1年に向けての具体的な目標を教えてください。
まず研究面では、現在取り組んでいる教育委員会の組織開発に関する研究をしっかりとまとめ上げたいと考えています。特に、指導主事のワークエンゲージメントを高める要因について、新しい知見を提供できればと思います。
実務面では、大学院で学んだ理論やフレームワークを、より積極的にクライアントの組織変革に活かしていきたいですね。教育分野と企業の組織開発をつなぐ新しいアプローチの開発にも挑戦したいと考えています。また、これまでの経験と研究成果を体系化して、近い将来、本にまとめていきたいと考えています。理論と実践の両方を知る者だからこそ提供できる視点があると信じています。
あとがき
長谷川さんの歩みは、教育とビジネスの領域を行き来しながら、独自の視点を築いてきた軌跡といえるでしょう。キャンプリーダーとしての経験、世界一周での冒険、企業での苦労、そして教育現場での実践。それぞれの経験が、現在の研究テーマや問題意識につながっていることが印象的でした。
社会人大学院での学びは、単なるスキルアップの場ではなく、これまでの経験を理論的に振り返り、新たな可能性を見出す機会となっているようです。理論と実践を往復しながら、組織と人の成長を支援する。その姿勢に、社会人大学院ならではの学びの深さを感じました。